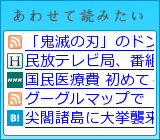新たな高等教育機関 #とは ― 2015年06月06日 09時27分24秒
なるべく毎日更新するつもりだったのに一週間も穴を開けてもうた…。
こうしたなかで、安倍総理大臣は、生産性の向上には、企業の投資に加えて、政府を挙げて人材の育成に取り組む必要があるとして、高校の卒業生などを対象とした新たな高等教育機関の創設を目指す意向を固めました。
この高等教育機関では、産業界のニーズに即した職業教育を行い、IT技術や金融などに関する実践的な能力を持つ人材の育成を目指す方針で、来年6月をめどに制度設計を終え、速やかに必要な法案を国会に提出したい考えです。
はぁ。
はてブなんかでは「専門学校と何が違うの?」的なコメントが多いですね。実際問題として既存の専門学校との差別化が図れないようであれば創設の意義はないでしょうから、その辺をいかにアピールするかが政治的には重要になっていくのでしょうが。
このニュースを読んで真っ先に思い出した記事 >http://t.co/lxbSXKHDDE 「ビジネスマインドで経営をする人々の大学は要らない大学だったので次々淘汰された」 / “安倍首相 新たな高等教育機関創設目指す NHKニュ…” http://t.co/DncxtNMu52
— T.MURACHI (@T_MURACHI) 2015, 6月 4既に専門学校というものが存在するにもかかわらず、こういう内容であくまで「新たな高等教育機関創設目指す」と書いているわけですから、そういう意味では、おいらとしてはむしろ、かつての株式会社立大学のようなものを連想したわけです。おいらがブコメで上記のように書いたのは、よーするにそういうことです。
2004年に小泉内閣時代に構造改革・規制緩和路線の中で「株式会社立大学」が構造改革特区に認可された。
その後についてご存じだろうか。
LECリーガルマインド大学は2004年に開学、全国14キャンパスを大々的に展開したが、まったく学生が集まらず、2009年に定員160名のところに18名しか志願者が来ないで募集停止となった。
2006年開学のLCA学院大学も志願者が集まらず2009年に募集停止した。
TAC学院大学は2006年に開学申請したが、記載不備で却下されて消えた。
実務に通じたビジネスマンたちが旧弊な大学を叩き潰すために登場したビジネスマインデッドな大学はどこもたちまちのうちに市場から叩き出されてしまった。
だが、「ビジネスマインドで大学経営をする人々が次々と出てくれば、要らない大学は淘汰されるだろう」という命題は「ビジネスマインドで経営をする人々の大学は要らない大学だったので次々淘汰された」という皮肉なかたちでしか証明されていないということは繰り返しアナウンスすべきだろう。
もし大臣が大学教育にかかわる教育行政にビジネスマンを関与させようと望んでいるのであれば、その前にまず「株式会社立大学はなぜ失敗したのか?」についての説明責任があると私は思う。
そうそうこれこれw (←不謹慎) 結局のところ、やろうとしてることって、こういうのの二番煎じにならざるを得ないと思うんですよね。何しろ、「新たな高等教育機関」を名乗るわけですから、既存の大学では人気を博しやすい、「理工学部」とか、「情報学部」とか、「経済学部」なんてものは絶対に名乗ることはできないわけですし、そもそも大学ですら無いので「学部」という用語自体使いにくいわけで。
そこで、「学部」についてはとりあえず「コース」という言い方に変えればいいとして、そのコース名としてどういう名前をつけるのかというと、例えば「プログラミングコース」だとか、「システムテスト技術者コース」だとか、「証券取引コース」だとかってやってしまうと、分かりやすくていいっちゃいいんですが、あんまりにも具体的すぎて生々しくなってしまうというか、それだったらもう職業訓練校でいいじゃんっていう話にもなっちゃうわけですよね。
だから、専門性の高いエリート人材を育てる場ではあるけど、やってる内容としてはそれなりに学術的で崇高なもんだよっていうのを匂わせないといけない。となるとどんな名前になるか。例えば…、「ITディベロップメントアーキテクトコース」、「ヒューマンITコンサルティングコース」、「ビッグデータソムリエコース」、「国際ITコンコルドコース」、金融系だと…、「トレーディングビジネスコース」、「ファイナンシャルマーケティングコース」、「保険ビジネスデザインコース」、「デイトレーディングプライヤーコース」などといったところでしょうか。こういう感じの、意味が分かるような分からんような微妙なところを狙っていかざるを得なくなるんだと思うんです。最近は大学でもこういう感じの学部が少なくないですけど。
そもそも今回の話は経団連の総会
で出た話ということで、生産性の向上
のために、産業界のニーズに即した職業教育を
目指していこうということだそうですね。はてブでも「経団連の言いなりだ」的なコメントはいくつか見られましたが、そうした文脈の話である以上、産業界の (と、いうよりは財界の?) 意向についても確認しておくべきだと思います。
こちらは実際に公言されている建前…。
「大学はこんなに要らない。大学生といえぬほどの低学力のものたちを4年間遊ばせておくのは資源の無駄だ」というようなことをビジネスマンはよく口にする。
これから彼らからすればごく当然の要請である。
この6月に、首相召集の国家戦略会議で、財界人代表のある委員が「大学が増えすぎて学生の質が下がった。専門知識はおろか一般教養も外国語も身についていない。大学への予算配分にメリハリをつけ、競争によって質を上げよ。校数が減って、大学進学率が下がってもいい」と主張した。
そこには以下の様な目論見がある、というのが内田センセーの見解でした。
中等教育の内容を理解していないものは大学に入学させないという縛りをかければ、おそらく現在の大学生の3分の2は高卒で教育機会を終えるだろう。
そうすれば毎年数十万の低学力・低学歴の若年労働者が労働市場に供給されることになる。
財界人たちはこれを待ち望んでいるのである。
この最下層労働者群は信じられないほどの時給で雇用できる可能性がある。
今回の「新たな高等教育機関」が産業界に評価されれば、企業は大卒者よりもこちらの教育機関を出たものを厚遇するようになり、学生も大学よりこちらを目指すようになる。そうなれば「不要な大学」の自然淘汰、統廃合は進む——、彼らの青写真にそういうことも含まれているのであれば、なおさら専門学校や、かつて野望も虚しく散っていった株式会社立大学のようなものとの、明確な差別化が必要になってくるのだろうと思われるわけですが、さてどうなるでしょう、教育改革に名を刻みたい安部首相のお手並みや如何に。
そうそう、
@T_MURACHI 産業界から提示される「必要なスキル」が「コミュニケーション能力」となるに一票。いやぁ、今の大学のありようが良いとは思わないが、Job Descriptionがなく採用基準があやふやなまま高等教育を変えてもね……。
— しましま(偽) (@shimashima35) 2015, 6月 4こんな見方もあるわけですが、時間的拘束のゆるさに加え、それなりに成熟した責任ある大人として比較的自由な生活が許される大学生が、そのぬるま湯に漬かってきたが故に乱れた生活習慣を引きずり、更にはゆとり世代以降に見られる体育会系離れに伴い上下関係意識が薄れるなど、旧弊的価値観の企業からしてみれば労働者としては使いにくい、という見解 (というか偏見?) も根強いんじゃないかと思います。
「新たな高等教育機関」はこれへの反動として、おそらくは厳しい戒律とびっしりギリギリのカリキュラムにより学生をビシバシ鍛えあげる、軍人養成学校のような存在にもなりうるんじゃないかとも思います。一部の企業が研修で採用するような、体力を消耗する系の声出しをひたすらやらされる時間なんかも設けられたりするんじゃないですかね。結果として一部企業にとっては都合の良い兵隊がたくさん生まれるのかもしれませんが、そういう学校に魅力を感じる学生ってどれだけいらっさるんでしょうね…?
コメント
_ みっちぃ ― 2015/06/06 11:47:00
_ しま ― 2015/06/06 20:23:50
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/senmonshoku/
あと、濱口先生はこんな感じ。
http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2015/06/post-1723.html
アカデミックな場としての大学・大学院の高等教育・研究機関は必要ですが、本当にこれだけいるの?内実はどうなの?という点はもう一度考え直す必要があると思います。
企業は企業で大卒が本当必要なのか、専門性は必要なのかもしくは一般教養だけでよいのか、採用基準は何なのかなど考慮するべきじゃないでしょうか。
最終的には社会デザインの話にも及ぶわけで、濱口先生が提示している欧州型のエリート/ノンエリートを分けた社会というのも一つの選択肢になります。その場合、いまほど普通の大学は必要なくなるでしょうね。
あと、この分野だと東京大学の本田由紀先生が「教育の職業的意義」という書籍をだしているので読んでみるのもよいかと思います。
コメントをどうぞ
※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。
※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。
トラックバック
このエントリのトラックバックURL: http://harapeko.asablo.jp/blog/2015/06/05/7663006/tb
※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。