コミュニケーション疲労と心の距離 ― 2007年03月22日 11時40分02秒
mixi 疲れとかよく言われてるけどその辺に関する考察。
結論から言うと、コミュニティにおいて何らかの問題を共有している場合、そのコミュニティに参加する人のストレスは以下のように算出することができる (但し、かなり単純化している)。
コミュニケーション疲労度 = 問題の重大さ / (親交度 * 心の距離)
ここでよく誤解されがちなのは、親交度と心の距離との間に、反比例的な相関性がある、とする迷信である。人との付き合い方にある程度慣れている人であれば、親交の深い友人や家族などとも、心の距離を程よくとるようになる。そしてその結果として、コミュニケーションはより円滑となり、そして親交度はより深まることとなる。この論理が理解できないまま大人になってしまう人が、最近増えてきているのではないか、という疑念がある。
そもそも、「心の距離をとる」とは、どういうことを意味するのか? そこにまず誤解があるんじゃないかと思う。ありがちな誤解としては、「心の距離をとる = よそよそしく振舞う」という捉え方だが、これは日本人的事なかれ主義をベースとした社交的論理であり、必ずしもすべてのケースにおいて正しいわけではない。意味合いとして当てはまる、最もしっくり来る言葉は、「心の距離をとる = 相手の行動を許す」ということではないかと思う。逆にいえば、心の距離が近ければ近いほど、相手を許せなくなる、という論理である。
いくつか例を挙げてみよう。
休日に友達同士で誘い合わせてどこかへ遊びに行くことになった。行き先は何でもいいんだが、例えば、、、映画を観に行く、とでもしよう。映画は 13:15 から始まるが、昼飯も済ませておきたいし、移動の時間もあるし、ある程度時間に余裕を持たせておきたいというのもあるので、自分たちの住んでいる地元の駅に 10:00 集合ということにした。
ところが、待ち合わせをしていた友達のひとりが朝寝坊をしてしまい、約束の時間になっても来ないので電話をしてみたら、「ゴメン、今起きた。着替えてすぐ行くから待ってて~」などと言い出した。仲間達はみな、「しょーがねーなぁ」と苦笑いしながら、その寝坊介を待つことにした。
まぁ、実際の彼らの対応の仕方は他にもいろいろとあるだろうし、それ自体はその場のケースバイケースで動けばいいんだろうなぁとは思う。先に現地へ行くだけ行っちゃうっていう手もあるし、開演にも間に合わなければ先にチケットを買って中に入ってしまうっていう手もある。昼飯を食べる時間もあるのだから、この寝坊介君も今回のケースでは最低映画には間に合うだろう。だがそんなことはまぁどうでもいい。
問題は、この寝坊介君を、仲間達が許せるかどうか、という点に尽きる。ここで、この寝坊介君に対する不快感がより高い人ほど、心の距離は短いということが言える。
まずこの前提条件が分からない人は、とりあえず乳幼児と母親の関係を思い出してみて欲しい。
乳児は母親との一体感が強く、母親に対する心の距離は非常に短い。従って、ちょっとした事でも簡単に不快感を表し、泣きじゃくる。乳が出ないと泣き、おしめが濡れると泣き、抱き方が悪いと泣き、そして目を離すだけでも泣いたりする。
幼児は少しはマシになるが、それでも親に対する依存度は極めて高い。自分の願いが聞き入れられないと駄々をこねる甘えん坊さん。転ぶとすぐ泣き出すのも、側にいる親がなだめてくれることを期待しているからだ。
しかし成長してゆくに連れ、子どもはだんだん、親には依存しなくなってゆく。わがままも減り、泣くこともなくなり、逆に何かを手伝ったり、人によっては家族のためにできることをいろいろと考えるようになったりする。そうしてやがては自立し、人によっては親元を離れて生活するようになったりする。
そうやって親子は歳を負うごとに心の距離を離してゆくわけだが、だからといって親子の絆がそれによって同時に無くなってしまうわけではない。むしろ、正しいプロセスを踏んで着実に心の距離を離して行ったほうが、絆は返って深まっていたりすることの方が多い。
先ほどの友達同士のケースに戻ろう。心の距離の短い付き合いを求める人に問いたいのだが、もし、君がこの寝坊介君だったとして、自分のことを許せない友達がこの中にもしいたとしたら、君ならどう思うだろうか?
僕は寝坊なんかしない、と答えた人は、考えが浅いと指摘しておく。君は寝坊しないよう「気をつける」ことはできるが、それを以って絶対に寝坊しないでいられることを保証できるわけではない。例えば目覚まし時計の電池が切れてしまうことだってあるし、突然壊れてしまうことだってある。それに、明日の映画が楽しみで仕方がなくて、興奮して眠れなくなってしまうかもしれない。
ミステイクは寝坊だけに限った話では無いだろう。例えばインフルエンザに感染してしまったとしたらどうだろう? 映画は諦めざるを得ないだろうね。でも、それすらも許せないという友達がいたとしたら? 「健康管理ぐらいしっかりしろよ、ヲレは友達と約束するときは、絶対に風邪なんか引かないようにするぞ」なんつってね。
そういう付き合いは、非常に疲れる。そして、そういう付き合いの仕方を理由に、「俺達は本当に仲のいい友達だ」ということを証明しようとしているのだとしたら、それは恐らく、うまく行かないだろうとおいらは思う。
本当に親交の深い交友関係であるならば、こういう場面で個人を許せる余裕があるものだ。自分が何かミスをやらかして仲間達に迷惑をかけることがあったとしても、彼らはきっと許してくれる。その、「許してもらえる」っていう部分を信じているからこそ、安心して友達づきあいを続けられるのである。許すという事はすなわち、気にしないと言うことでもあり、それはある程度の心の距離がとられた状態である、ということの証明である。すなわち、心の距離が適切な長さを保っている方が、友達づきあいの親交度は深まるのである。
「許す」ということは、何もミステイクに限ったことではない。二つ目の例を示そう。
友達同士でおしゃべりをしていて、あるミュージシャンの話題になった。大抵の子はそのミュージシャンに対して否定的で、けなすようなことを言い合って笑っていたが、一人の子が、実はそのミュージシャンの大ファンであり、そんなことは無い、彼の音楽はとてもいいじゃないか、と反論した。
この反論はミステイクではない。が、この場にいた仲間達の何人かは、不快感を表すかもしれない言葉でもある。この反論が、実際にできるかどうか、そして、こうした反論に対して、どのように受け止めることができるかどうかでも、親交の度合いというのは見えてくる。
まず、反論できない、反論を許さないような空気のある友達づきあいというのは、論外である。君たちは友達でもなんでもないから、むなしい友達ごっこはやめて、もっと自分の没頭できる何かを探すことに時間をかけた方がいいよ、とおいらならアドバイスする。自分の言いたいことも言い合えないような仲なんてのは、友達ではない。
しかし一方で、この反論を許さない空気こそ、心の距離が短いことの証左でもある。何故なら、相手が自分と同じ意見・心境であることを、相手に期待し、望んでいるからだ。だから、その期待を裏切るような意見に出くわすと、その意見を口にする相手そのものが許せず、反発する。「どうしてそんなことを言うの?」ってことになる。で、そうやって嫌われるのが恐いから、誰も反論できなくなる。何で恐くなるのかといえば、自分がそれを許せないのと同様、相手もきっと、それを許してはくれないだろうという「不信」があるから。
さて、実際に反論を受けたとして、それに対する反応の仕方についても考えてみよう。ここで、徹底的に言い合いとなり、いや、俺はあいつらの音楽は糞だと思う、そんなことは無い、彼らの音楽は最高だ、と論争になったとする。彼らの親交度と心の距離は、どういう状態だといえるだろうか。
もしもその論争の後でも、彼らの友達づきあいとしての関係に対して影響が無いならば、彼らの親交度はかなり高いといえるし、同時に心の距離も十分な余裕があるといえる。彼らは、いくつかのことについて意見を違え、それで言い合いになるようなことが例えあったとしても、その程度で絆が失われることは無いことを知っているし、信じているからである。
それでは、この反論に対して、とりあえずその場は理解を示してみる、という対応についてはどうだろうか。
本当にその場にいる全員の気が変わり、そのミュージシャンのことを評価するようになったのだとすれば、それは単に反論した人間の説得力が優れていたという話になる。それはそれでアリだし、議論の種類によっては、最終的に全員の同意事項が形成されるというのはいいことでもあるのでまぁいいのだが、そういうことばかりでも無いだろう。とりあえずその場限りで理解したフリをし、事なきを得ようという「事なかれ主義の発動」が起こっているのだとすれば、その友達の親交度は決して高いとはいえないかもしれない。心の距離についても同様であり、内心で不快感を沸々とさせている可能性もある。そうなっちゃう人というのは友達付き合いでどんどん疲弊していくことになるし、その一方で常に何とも言えない「寂しさ」を抱き続けることになる。
もちろん、反論が適当に受け流されることがあったからといって、必ずしも親交が浅いわけでも距離のとり方が下手なわけでもない。論じている物事自体がその友達の間では取るに足らないことであったり、あるいは既に同意事項として、「あるミュージシャンを好む奴もいれば、嫌う奴もいて当然だ」という認識があったりするならば、そうか、お前は好きなんだ、ヘェ、で完了でもまったく問題ない。
しかし、いつも仲良くニコニコやって、いがみ合うことがまったく無いのが「良い友達づきあい」なんだと言う前提のもと、おっかなびっくり友達づきあいを演じているのだとしたら、それは悲しくも虚しいことだ。もっともっと、本気でモノを言い合えるようでなければ、本物の仲間を得たということにはならないのだ。
では、友達同士、本気でモノを言い合えるようになるには、何をどう、気をつければよいのか。実際には何かを意識して気をつける必要は無いはずなんだが、敢えて言うならば、自分の意見を持ち、反論すべきは反論するよう心がけること、なんじゃないかと思う。そして、相手を言い負かそうとするのではなく、相手の話もしっかり聞き入れて、常に自分の考えの正当性も疑ってみること。何はともあれ、誠意ある対話のできる人間は、どんな考え方の持ち主であれ、それなりに人に好かれるものだと思う。
しかしそう考えてみると、実は論理的思考に長けている人間ほど、人とのコミュニケーションにも長けているものなんじゃないかと思えてくる。論理的思考に長けているならば、発言と、発言した人とを、完全に切り分けて考えることができるはずだからだ。そういう人は、意見を違える相手を、意見を違えるからという理由で嫌うことはあまり無い。俺は右翼だしあんたはどー見ても左翼だけど、それはそれとして、飯はうまいし酒もうまい。こんないい店知ってるあんたとは仲良くなっておきたいねぇ。みたいな。(めちゃくちゃな例えだなw)
コメント
_ 久遠 ― 2007/03/26 19:57:37
_ T.MURACHI ― 2007/03/27 00:41:41
例えば仲間として付き合いを始めた人間が、いきなりなんの断りも無くタバコを吸い始めて、しかもその吸殻をヘーキで床に落としたりし始めたら、確かにおいらは彼には敬遠したくなる。それは確かに心の距離をぐっと離すということになるわけだけれども、でもそれは仲良くするための距離のとり方ではなくて、なるべくお関わりあいにならないようにするための距離のとり方だ。
それに対して、そういうほぼ初対面の相手に対して意見を述べるというのは、その人との縁を切り離すわけにはいかない何らかの事情がある場合を前提とするんじゃないかと思う。そうでなければ、おいらだったらいちいち折衝せずに敬遠してしまうと思う。もちろん、その辺の判断基準は人によって違うだろうし、久遠ちゃんの場合なら結構意見しちゃうことの方が多いのかもしれないけど、とにかくそうやってお互いをけん制しあう作業を繰り返すことによって、お互いの心の距離のとり方を調整するという過程を経た上で、結果として仲が良くなるかどうかが決まる、というのが、コミュニケーションのわりと正しいプロセスなんじゃないかと思う (もちろん、かなり単純化されたモデルであって、実際はそうそう単純な話ばかりじゃない、って言うかも知れないけど、基本はあくまでそういうモデルなんじゃないかな)。
肝心なのは、「仲良くなってから相手を知る」というのは順序が逆だろう? ということ。まず礼儀があり、時を経て相手を知るうちに、いろいろなことが許せるようになっていく (つまり、礼儀の一部が省略可能になる)。そうやって仲間ってのは形成されていくものなんじゃないかと思う。自然発生的にはね。
もう一つ。「許せる」のと、「受け容れられる」のとは違う。さっきも書いたけど、仲間にならないことを前提とした許容は、よーするに無関与であることを示す。無関与になれないからこそ、許せないのだと思う (無関与に徹しようと思えるほど、心の距離を切り離すことができない)。それに対して、仲間になることを前提とした許容は、「あまり気にしない」ということ。同じようにタバコを吸う人間同士であれば、確かにそこはあまり気にしないだろう。だから、「価値観に依存している」というのは、実は正解。
問題は、自身の価値観を無視して、まず仲良くなろうとすることから始める付き合い方であるが故に、後にお互いの価値観の折衝がコミュニケーションを行き詰らせて、トラブルにまで発展するケース。あるいはトラブルに至らず、お互いが我慢しあった状態が続くことによるストレスの蓄積。どちらにしても (いや、どちらかというと後者の方が)、不健康なコミュニケーションだと思うし、それは絶対に避けるべきだと思う。
_ T.MURACHI ― 2007/03/27 00:54:51
なお、キレイゴトを一切排除する為、生やさしい表現はなるべく避けて書いています。念のため。
_ 久遠 ― 2007/03/27 03:06:34
ただ、ちょっと論点がずれてるんだが、私は、「心の距離が近ければ近いほど、相手を許せなくなる、という論理である。」が間違ってんじゃない?って思ってるのね。
自分にとってクリティカルな事なら、赤の他人でも気になるし、どうでもいいことなら、別にいちいち突っ込もうとは思わない。
遅刻の許容もそう。
相手が友達でも、遅刻したら迷惑だし、「許してもらえる」っていう部分を信じていられたら、それこそふざけんなって話し。
・・・って、思う人だっているでしょ?
私にとってのたばこのように。
コミュニケーションを論じる上で、まず相手との心の距離感に重きを置いてるけど、実際それってほとんど意味ないファクターだよね? 遅刻やたばこや、議論が各人の価値観に大きく委ねられてることを考えれば。
たぶんね、言いたいことはそれ程違わないと思うんだけど、距離って言葉から感じることが、違うんだと思う。
むらちゃんの、書き方だと、適切な心の距離を保つこと、それが相手への許容につながり、円滑なコミュニケーションになる。その距離を測るために、対話が必要だ。って感じでいい?
私は、そんな付き合いを理想と思えない。
ぐっと、相手に踏み込んだ方が、相手の価値観は見えてくるし、そこから自分の価値観との摺り合わせになるんだと思う。
「お互いの価値観の折衝がコミュニケーションを行き詰らせて、トラブルにまで発展するケース。あるいはトラブルに至らず、お互いが我慢しあった状態が続くことによるストレスの蓄積」
これは、むしろ、お互いに距離を取ってる人同士の方が起こりやすくないかい?と。
そして、二つめもだいぶむらちゃんの恣意的な感情が働いてるようで違和感を感じる。
まあ、Mixiがどうのとか、流行に乗じるつもりはないけど、ネットだからって問題かね?
「ネットではその形は大分違う。ブログにせよ掲示板にせよ、まず相手の表明する意見に対する返答から始まる。」
これ、むらちゃんの個人的な感想だよね。
日記をいくつか読んで、プロフィールを見て、それで友達になりませんかって使い方をしてる人もいるよね。
それは、リアルで友達になるのと、どこまで違うのか、私には違いが分からない。
リアルにも、名前さえ知らないが毎月一回は飯一緒に食いに行く友達もいるし、ネットだけで相手が男か女かも知らんが、メッセで会えば必ず1時間以上話す相手もいる。
どっちが主流かは知らんけど、だから、ネットで対人関係に悩んでしまう人が多いのか・・・本当に多いのか?
本当に危険なのか。 いまいちぴんとこない。
怪しい人には気をつけましょう、はネットでもリアルでも一緒でしょ、と。
唯一、なぜかネットの方が安全である、と錯覚してしまいそうな人が危ない、とかはあるかもしれんが・・・
それは、コミュニケーション云々の前に、道具の習熟度の問題でしょ、ってことで。
たぶん、最初のもやもやは、
「心の距離が適切な長さを保っている方が、友達づきあいの親交度は深まる」
はおかしくない?
せめて、もう少し納得できる例を提示して欲しい。
ってとこなんだと思う。
これの例として、遅刻の許容はないだろ、と。
もう少し適切な長さを保っている・・・が、どういうことなのか、知りたい。
遅刻の許容は、ただ、そいつが暇だっただけじゃん、と区別がつかない。
にもかかわらず、許容できないタイプを赤ん坊に例えて、余裕がないと論じてる。
それは、自分の価値観的に遅刻が許容できてるだけなのに、それを許せない人間の価値観を認めていないように取れる。
本題はそこじゃないんだろうけど。
少し内容が散ってしまったが、違和感があって確認したかったのはそこ。
遅刻を許せないのは、心の距離が狭いからだと断じるのは、まさしく自分の価値観を押しつけてないか?と。
そこが、そういう意味じゃないんだよーっと解説してもらえれば、安心して眠れますw
_ T.MURACHI ― 2007/03/27 15:33:53
心の距離って言葉については、他分捉え方が違うんだと思う。おいらはブログ記事の中でも最初に「心の距離をとる≠よそよそしく振舞う」って書いてる。久遠ちゃんのいう、「むしろ、お互いに距離を取ってる人同士の方がトラブルになったりストレスになったりしやすい」っていう状態は、距離をとるっていうことを何か勘違いして行っている結果なんじゃないかと思う。
極端に言えば、相手の逆鱗に触れないようにおっかなびっくり接している状態は、おいら的には正しい距離の取り方じゃない。少なくとも、仲間として接し続けることを前提とした距離の取り方じゃない。
逆に、「ぐっと、相手に踏み込んだ方が、相手の価値観は見えてくる」からこそ、普段の距離感というか、間合いのとり方が重要になってくるんじゃないかと思う。この辺、@DRKが「異質さの寛容」という言い方を使ってるけど、これは割りとしっくり来る表現だったりする。他人が自分とは違う部分があるってことをわきまえていて、それを受け容れられるか、または正面から折衝することができるって覚悟があるからこそ、相手に踏み込める、っていう部分もあるんじゃないかと思う。これが、最初から自分と同質であると決め込んだ状態で踏み込んでいくのとでは、結果として自身や相手に降りかかってくるストレスの度合いは大きく違ってきちゃうんじゃないかと思う。
おいらが言ってる「距離」ってのはそういう部分で、それをイメージしやすいようにと出したのが乳幼児の例だったわけだけんども、やっぱり分かりにくいかのう。
遅刻の例えについては、時間感覚を要点として読まれてしまうと確かに誤解になってしまう気がする。どちらかというと約束事に対する寛容とか、個人の不測の事態に対する想像力や機転とかって辺りについて書いたつもりだったんだけど (そうじゃなければその後に風邪引いていけなくなっちゃったみたいな例を書く意味が無い)、ただどっちにしても「性格の問題」とは言えなくもないし、「そういう人にはご用心」みたいな話に解釈されてしまうとそれはおいらの意に反する。
逆説的には、「許せないということを許せ」っていう面もあるけど、それをやたらと重ねていった状態で「うまく距離をとっている」としてしまうのはさすがに違うと思うのよね。それって単に我慢しあっているだけじゃんっていう。で、その我慢しあう部分をどうにか解決する為の手段の一つとして、対話があるんじゃないの? ていう。その対話の結果として、納得の上で合意し、妥協しあって、ある程度は譲らなきゃいけない部分ってのも、現実的には出てくるわけだけど、その譲らなきゃっていう部分にストレスを感じていて、それが無いコミュニケーションっていう意味でネットに幻想抱いているんだとしたら、それは違うだろうと。
つまり、付き合い上のストレスなんてことを考えもせずに周囲の子と友達づきあいすることを始めた子供が、いろんなストレスを体感した上で他人との距離のとり方を覚えてゆく過程と、「距離を置かない付き合い」を求めて mixi とか始めたのに、マイミクに入れたおともだちが自分の日記を見ただの見ないだの、コメント書いたの書かないので揉めて、結果、まぁそういう人もいるよなっつって寛容になっていく過程と、実際的にどれほどの差があるのかと。で、そういう「寛容」を認めたくなくて、「読み逃げ禁止」みたいなことを言い出す人がいるんだとしたら、それはさすがに不健康なコミュニケーションになってしまうんじゃないの? っていうこと。これは、遅刻に至るまでの状況について思いの至らない人、コメントを書かない (「書けない」なのかもしれない) 人が置かれている状況について思いの至らない人、という意味で重なる。もちろん、それが悪いなんてとても言う気にはなれないんだけど、ただ、そういう部分で厳しい人とは、正直付き合いにくいな、とは思う。
もちろん、遅刻してしまうのは失礼なことだし、極力遅刻しないように勤めるべきだ。マイミクに入れるだけ入れてもらって、マイミク向けの日記を読むだけで反応なしってのも失礼なことなのかもしれないし、反応を楽しみにしていることを知っていて、機転の効いたコメントを返せることがあるならば、たまには反応してあげてもいいんじゃないかとは思う。それは確かかもしれないけど、でもそういったことのすべてを尽くしあうのが仲間ってものなのか? それは違うでしょう。求めるな、ってのは確かにおかしいけど、どっちにしても極端なのはよくない。
で、「どれほどの差があるのか」って書いておきながら、それでもネットから始まるコミュニケーション (っていうか、友達づきあい) にどうしても懐疑的になってしまうのは、確かに自己矛盾なのかもしれないんだが、それでももう少し考察を重ねてみたいと思う。
ていうのは、「日記をいくつか読んで、プロフィールを見て、それで友達になりませんか」って、それだけの情報を見ただけで相手を知った気になって友達になりたがってしまうのがネット上での友達探し&友達づきあいなんだとしたらやっぱり危険なんじゃないかって思ってしまう。初対面の人がどういう人なのかは普通は知らないから、対話を繰り返すことによって、相手がどういう人間なのかを知ろうとする。つまり、対話が行われる段階では、そもそも仲間になっていないかもしれないわけだ。仲間にならなきゃ対話はできないって思い込んでしまっている人は多いような気はするし、本当はネットがどうこうということじゃなくて本質的な問題はそこにあるんじゃないかって言う気もするんだけど、一方でネットやケータイが生み出す「流動的な付き合い」が、その辺の根底での考え方に変質をもたらす原因の一つになっている可能性は拭えない。
日記にせよプロフィールにせよ、そこに書かれていることは恐らく書いている人間の「見せたい自分」の自己表現だ。対話はそのバリヤーを時として突き崩すからこそ、その人の人となりが見えてくる。だからこそ、その人とどう付き合うか、その距離感を、自分なりに見出すことができるんじゃない?
だのに、日記やらプロフィールやらを読んだだけで、あー、この人とは仲良くなれそうーとか言ってイントロもなしに「友達になりませんかー」ってのが健全な付き合い方なのかと言われると、まぁ本当に子どものうちはそれも致し方ないかなとは思わなくも無いけど、おいらには恐くてできねーだす。
で、そういう付き合いの始め方が、ネットという道具を介するとやりやすくなってしまうのだとしたら、それってどうなのよ? とどうしても思ってしまうわけですよ。
事件性のあるトラブルがどうこうという話については、実はそれほど気にしてない。実際日本では物凄く少ない (週刊ミヤダイ http://www.tbsradio.jp/miyadai/popup.html 2007/2/16 更新分参考)。ただ、ネットで仲間探し (友達探し?) をしたいというニーズがあって、その為の最適な道具が mixi なのか? っていうと、それはどうかと思うし、もっと対話を重視した道具は作れるかもしれない。その辺、システムとしてうまく作れないかっていう部分には結構興味深く思う。
ちなみに、@DRKの言う例外事項については、個人的には友達づきあいに関する今回の話題とは切り離して考えるべきなんじゃないかと思う。確かに金の貸し借りとか良識・順法とかは人として大切なことだけど、人付き合いとして大切なことなのかというとそれはまた別問題だし。
_ 久遠 ― 2007/03/27 19:22:10
逆に、むらちゃんを混乱させてしまったか;
結論は同じじゃない?と前もって断ったのに、似たような結論を延々と言ってる割に、肝心なこちらの疑問に対する答えはぼけてるしなぁ。
ちなみに、
「遅刻の例えについては、時間感覚を要点として読まれてしまうと確かに誤解になってしまう気がする。どちらかというと約束事に対する寛容とか、個人の不測の事態に対する想像力や機転とかって辺りについて書いたつもりだったんだけど」
ってのは、それも含めて違うんじゃない?って話だったんだけど。
最初の、
「寝坊介君に対する不快感がより高い人ほど、心の距離は短い」
これは、むらちゃん流に言うなら、相手が不測の事態に陥ってること等まで考えれば、不快感は減少するはずだってことだよね。
けど、待たされることを被害と感じるなら、それは相手に過失があろうがなかろうが、感じるもんは感じるんじゃない?
そのストレスを我慢するかどうかは、ともかく。
また、約束事に対する慣用も一緒。
結局はその重さを当人同士がどう考えてるかによる。
もちろん、そういう人にご用心じゃなくて、寛容さに対する例としてどうなん?って話し。
後、釣りのMixi。
むらちゃんの結論がまさしく、結論なんだけど、つまり極端なのはよくない。
これを私の視点から見ると、
(別に、やぶろうと思えばなんら強制力のない)読み逃げ禁止と書いた人と、
その価値観が自分にとって異質だってだけで、相手への寛容に欠けるだの、不健全なコミュニケーションだの、と完全否定的に断じる人と、
どっちが極端か?って話し。
正直ね、自分のページなんだから、自分の流儀に従って。嫌なら来ないで。ってスタンスは別に違和感ないのね(読み逃げ禁止そのものは共感できないけど)
それより、それに対して強要するのはどうよ?ってつっこみ入れる方が大きなお世話じゃね?と思うですよ。
むらちゃんは多分、譲らなきゃっていう部分にストレスを感じていて、それが無いコミュニケーションっていう意味でネットに幻想抱いている人に対して、そんなことはないよ、と言いたかったと思うんだけど、それにしては説明不足も過ぎるだろう、と。(個人的には、そもそもそんなの本当にごく少数だとも思うし)
私の感想からすると、あれ、ただのワガママな人だよw
で、ああいう人はリアルでもワガママだよw
Mixiやネット全般のように論じるのは誤解の元ですよ、って感じかなぁ。
そういう意味でね、ごく一部の限られた価値観を抽出して、疲労度だの心の距離だの、なんだかすごく一般的な話しのように論じたのが、ひっかかったのかも。
なんだろ・・・プログラマ的には、その仕様、ぱっと見シンプルで分かりやすそうだけど、機能のほとんどは例外処理ばっかで使いもんになんねーじゃん、って感じのとんでも仕様を見たときのつっこみたい感、と言いましょうか・・・
後は、ネットの件はむらちゃん本人も自覚してるみたいだし、何というか個人の感覚に踏み込んで議論しても仕方のないことだと思うんだけど、1ネットユーザーとしては、
ネットで仲間を作ることと、
譲らなきゃっていう部分にストレスを感じていて、それが無いコミュニケーションっていう意味でネットに幻想抱いている人を、
同じカテゴリーで括るのやめて;
本人がどこまで意識してるかわからんけど、括ってるようにしか思えない記述を散見するので。
それと、
「日記にせよプロフィールにせよ、そこに書かれていることは恐らく書いている人間の「見せたい自分」の自己表現だ。」
これは、リアルとどこが違うのか問いたい。
誰だって、現実だって、基本的に他人と接するとき、「見せたい自分の自己表現」じゃない?
おしゃれだってするし、猫をかぶってる人もいる。
だんだんと、相手がわかってくる。
それは、掲示板やメールで話してたって一緒。
どんな友達も最初は他人。
趣味が一緒だから、友達になりませんかー?
は、どこが不健全なの?
Mixiの友達になりませんか?は、知り合うためのきっかけなんだと思うよ。
むしろ、リアルでむらちゃんはどんな風に新しく友達を作るのか知りたいw
ネットでも、対話をするかしないかは各個人の話しで、システムの問題じゃないよね。
Mixiだろうが、なんだろうが会話はできるよね。
今も、ネットで議論してるじゃんw
正直、これは友達作りに対するスタンスの差なんだろうと思う。
むらちゃんはたぶん、友達とこじれるのが嫌なんだよね?
だから、友達だかなんだか微妙な状態の輪をいくつも増やすのは負担だし、そういう意味で現状のネットのシステムは、自分の仕様を満たしていない(と感じている)
その割に、リアルに何故幻想を抱けるのかは疑問だけど。
(個人的には、直接会話して見抜けるようなことは、チャットでも見抜けると思ってるので)
まあ、ここはあんまり白黒つけるようなことでもないと思うので、(私のネット感も特殊だろうし)、、「仲良くなってから相手を知る」というのは順序が逆だろう? って考え方じゃ、友達作るの大変そうだなぁ;って感想くらいっす。
・・・結局、「心の距離」のむらちゃん流定義は、理解できずに終わりそうかなぁ
_ T.MURACHI ― 2007/03/27 22:05:36
おいらは友達ってのは自分から作ろうとして作るものなんじゃなくて、自然発生的に勝手になっちゃうものなんだと思っているのよ。もちろん、友達になるってのは悪いことでは無い、むしろ本当にちゃんと友達になっているんであればそれはそれで良いことなんだろうけど (良いことばかりでも無いかもしれないけど ^_^;)。
一方で、例えば趣味とかからの繋がりで新たな仲間を作ろうとするための呼びかけってのはそもそもインターネットが生まれるよりはるか昔からいろんな形で行われていることだし、学校内外のクラブ活動からロックバンドからボランティア活動やら企業結社・リクルートやらに至るまで、それによってコミュニティが形成されていろんな活動に発展したりしている。
でも、例えばいくら同好の士が集まった場だからといって、クラブ活動に参加する全員と仲良くなれ、といわれても、なかなかそういうわけには行かない。同好の士としては間違いなく「仲間」だけど、それと友達になるかどうかというのはまったくの別問題だと思う。
言うなれば、例えば楽器やってる人間に向けて「一緒にバンドやらね?」はアリ。お互いの腕前や目指す音楽の方向性にお互いが納得いくならば、そこでバンドを結成するのもいいでしょう。
でも、「へぇぇ、君も楽器やってるんだ。俺達仲良くなれそうだね。」とか言っちゃう人には、警戒してしまう。「楽器やってる同士」というだけで、いきなり友達にはなれない。もちろん、その後に対話があって、本当に気が合う奴だと思うに至れば、話は別だし、そうした対話を前提とした社交辞令のつもりで言っているんであれば、話は別だよ。
だから、もとよりネット上で「仲間を探している人」というのは今回の話では眼目においていないんだけれども、もしかしたらほとんどの「ネット上で交流を求める人」というのはそういう形のものであって、最初から「仲良くなること」前提で友達探しをする人っていうのは、それ自体がレアケースなのかもしれない。もし、そうなんだとしたら、確かにおいらが書いていることの意義ってのはかなり小さいのかもしれない。
友達になっちゃった人とこじれるのは、もう嫌だねぇ。(T-T)
おいら的には、こじれてしまったというつもりはこれっぽっちも無いんだけどね。
読み逃げの件に関して言えば、確かにどっちも極端だし、おいらももともと 2ch やはてぶでの反応に対しても「思考停止じゃね」とさえ指摘していたわけだけれども、一方で、経緯まで含めて考えれば、どっちの気持ちにも一定の共感はある。
「ともだち100人できるかな?」じゃないけど、被マイミク数稼ぐ為に手当たり次第マイミク登録せがんで、マイミク向け日記を読むだけ読んでニヤニヤしているような奴がいるんだとすれば、それは確かに気持ち悪い。
一方で、「友達なんだから僕の痛みも理解してくれるよね」とばかりにマイミク向けにイタい日記を乱発して、それに対する反応が無いことをあからさまに嘆くような人とおつき合いするのは、あまりにも重いし、辛い。(心が近すぎる、っていうのは例えばこういうことを言いたかったんだけど、どっちかというと「近いと思い込んじゃっている」の方がニュアンスとしては通じやすいのかなぁ、でもこういう人って大概、至って真剣なんだよね。だから「お前が近いと思い込んでいるだけだ」と断ずるのも、何か違う気がする。その人自身が近いと感じているのなら、確かに近いんだと思う。実際近いからこそ、お互いに辛いんだと思う。)
で、そうしたことから自身を守る手段として、こうしておけば大丈夫っていう解なんてあるわけが無いし、それは各々のケースについて都度考えながら自分の責任で行動しなきゃならない。何しろ、相手がいることだし。とはいえ、自分が一番大切なのだから、その行動が結果として相手を傷つけることになるのだとしても、それを覚悟の上で行動しなきゃいけない場合だってある。
だからこそ、「読み逃げ禁止」的な村八分への動員も、「読み逃げ禁止は無いだろ」的な村八分への動員も、慎重にならなきゃいけないんじゃないかと思う。それはもう、社会として成熟してないだろうと。オタク差別みたいなのと本質的には変わらなくなっちゃうよ。
そんなところかなぁ。
_ T.MURACHI ― 2007/03/27 22:33:57
> その割に、リアルに何故幻想を抱けるのかは疑問だけど。
> (個人的には、直接会話して見抜けるようなことは、チャットでも見抜けると思ってるので)
これはもう、完全においらの感覚の問題であって、人によって違うんであろうことは当然のことなんだけど、一応。
個人的には、リアルにせよそうでないにせよ、会話だけで 1週間根詰めてやり取りすることよりも、たった一回食事を共にすることの方が、相手の多くを知れる (見れる) ように思っています。
仕事や旅なら尚更。。。
おいらの言う「対話」には、そこまで含まれるのよ。(って見事な後出しじゃんけん…)
言葉で問い、知ることよりも、行動を見て知ることの方が、経験的にははるかに信用できてしまう。
# だからこそ、おいらが超いーかげんな人間であることは、身内ならみんな見抜いちゃっているわけですが ((((/;^^)/ 。
コメントをどうぞ
※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。
※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。
トラックバック
このエントリのトラックバックURL: http://harapeko.asablo.jp/blog/2007/03/22/1335020/tb
※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。
_ ふとももおれたー - 2007/03/24 11:43:57
コミュニケーション疲労と心の距離
(国民宿舎はらぺこ 大浴場さま)へtb。
大雑把に主旨を示せば、
いわゆる「読み逃げ
_ ぶれーくだんす - 2007/03/27 15:07:37
さて、今回はいつもどおりの「ひとりごと」でございます。
てゆーか、我ながらいつも波に乗るのが遅いんですがw
読み逃げ(国民宿舎はらぺこ大浴場)
コミュニケーション疲労と心の距離(同上


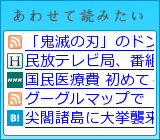





例えば、一緒に遊んでいて隣でもくもくタバコ吸ってる友達を許せるのが、心の距離を正常に保てて、少し控えろよと許容できずにいる人間は距離が短いん?
例えば、たまたま会ったときに体臭が臭った友達に、おまえ風呂入ってからこいよ、っていうやつは心の距離が短くて、安心してつきあえるためには許すことが必要なん?
許す・許さないと、気にする・気にしないはそれぞれのケースや個々の価値観によってだいぶ差異がある気がして、遅刻の許容を理由に、心の距離を測るのって、だいぶ自分本位の価値観に依存してるような気がするんだけど、どうなんでしょ?
やっぱ、自分があげたような例でも、許す前提が必要なん?
私は単純に、自分の気にならないことは文句言わないし、文句あったら、友達だからってそれを理由に控えることはないよ。
それでも、単純に気になるとこと気にならないとこの価値観が似通ってるから、つきあっていけてんのかなぁと思ったんだが、どうなんでしょ?
・・・それとも、ここでいう疲労度は、もっと八方美人ちっくな人間を前提にしてるのかしら;