民主主義と匿名実名論 ― 2007年12月16日 01時18分56秒
賛成できる部分と、できない部分があります。賛成できる部分とは、匿名性の過度の尊重がネット上での言論の敷居を上げてしまっている可能性の指摘です (←こう書いておけば、この記事に対して匿名でいちゃもんをつける連中の行動が、おいらにとっては「してやったり」になるw)。匿名性の需要が衰退していく可能性についても、否定はできないという程度には賛成です。賛成できない部分とは、現状の社会風潮における匿名性の需要を過小評価している点と、Wikipedia 上の記事の質がものによっては低い理由を匿名性に見出している点です。
Wikipedia の記事の質が低い理由
Wikipedia は、民主的な集合知を期待することを前提としたシステムです。これは、例えば誰かが誤った内容 (勘違い、嘘、または出展の伴わないあやふやな情報) を書き込んだとしても、その記事を閲覧する他の多くの人がその間違いを訂正し、その繰り返しが結果として、記事がより正確で質の高い内容を確保するように仕向けられている、ということです。
このシステムは、それに関わる書き手の人間の多くが善良で且つ聡明であることを前提とし、または期待しています。Wikipedia が不幸なのは、実際には多くの人はそれなりに善良かもしれないが、決して聡明ではないという点です。
Wikipedia 上の記事の質が低くなってしまう理由として考えられるものを、以下に列挙して見ます。
- あまり閲覧されない記事である。
- 真実を知る人よりも、誤解している人のほうが多い記事である。
- 出展となる一時情報が少ない記事である。
- 企業が Wikipedia 運営元に法を盾に脅しをかけた。
極端なケース (馬鹿が荒らしにきたとか馬鹿がふざけて追加したとか当事者が自身に都合のよいように書き換えたとか) もちらほらと見かけるが、それこそ民主主義的原則で浄化されることが期待できるのでここでは無視するとして。
1. については、これはもうどうしようもないと思う。誰も見ないような記事であれば、誰も内容を気にしようとはしないだろう。それは、執筆者が匿名であるか署名しているかに関わらず、同じことだ。
2. は、編集合戦になればまだいいほうで、誤解されたままの内容がそのまま放置されたり、更に悪いことには Wikipedia が誤解の発信源になってしまうこともしばしばある。こうした記事に対して、当事者が自身のブログなどで指摘し、その指摘を受けて内容が訂正されるという動きも時々見かける。悪意を以って恣意的に記述されるようなケースについては著名を求めることである程度防止できそうだが、そうでないケースも多いのではないかと思う。
3. は、Wikipedia が果たそうとする社会的使命に通ずる問題で、要するに Wikipedai 自身が一時情報となることを放棄しているが故の問題である。Wikipedia 固有の問題であり、この問題に対して、立場を明かした人間による著名付きの記述が得られる仕組みを設けるというアイデアは、割とイケてるのではないかと思う。
Google の knol (ニュース記事とかはすぐ見つかるんだが knol 自身の url がわからん…) はそういう部分を埋め合わせるシステムとして考案されたようだが、一方で、同一トピックに対して多数のユーザーが記事を執筆した場合、レーティングの仕組み、即ち結局は民主的裁量に委ねられることになる。企業に関する内容など、複数の当事者を名乗る人間がまったく違うことを書く記事が乱立するという事態になれば、結局は読み手に高いメディアリテラシーを求められることになるわけで。。。それでも 2ちゃんねる情報を鵜呑みにされるよりはマシか?
4. については、これはもう匿名云々の問題というよりは運営側の裁量の問題。書き手がいくらがんばっても Wikipedia 運営者にヒヨられてはもうどうしようもないというかなんというか。
まだ多くのユーザーが、匿名性の必要性を感じている
プライバシーって言うのは、「知られたくない自分」を隠すことによって、「見せたい自分」を作る権利の事。人間、常にまじめな議論ばかりを繰り返しているわけではなくて、たまには普段見せていない裏の顔を演じてみたくなったりもするわけである。
その裏の顔っていうのは、何も特定のブロガーのコメント欄に「アフォ」だの「氏ね」だの書き込んで憂さを晴らすみたいなネガティブな行動ばかりではなくて、例えば絵や音楽や小説などの作品を作って公開したり、それこそ人によっては糞まじめな議論に参加する、って言うことであったりもするわけだ。
普段は普通の子を装っているのに、実はパソコンでアニメっぽい CG を描いているなんて知れたら友達に敬遠されるかもしれない。でも、せっかく描いた絵を誰にも見せられないのは寂しい。
普段はギターとか弾いて生楽器生演奏マンセーとか言っているのに、実は DTM でシコシコ打ち込みで作曲するのも好きだなんて知れたら友達に敬遠されるかもしれない。でも、せっかく作った楽曲を誰にも聴かせられないのは悔しい。
普段はテキトーで軽い奴で通っているのに、政治の話とかを熱く語ったりしてしまったら同僚に激しく引かれるかもしれない。でも、文化審議会著作権分科会法制問題小委員会で通過しようとしているダウンロード違法化にはどうしても賛成できないし、それ以外にも著作権に関してはいろいろと言いたい事もあるんだ。
匿名ってのは、上記のような (少なくとも日本では) 割とありふれた場面と感情に直面している人間が使うものであり、これを許容しないシステムが広く一般に普及するような状況というのは、まだまだ先のことなんじゃないかと思う。
もちろん、近い将来、IPv6 が普及することで、IP アドレスによる個人の特定が技術的に容易になる世界は訪れるだろうが、上記のような一般的な要求に基づく匿名性としては、そうした個人の特定の可能性まで拒んでいるわけではないと思う。
匿名性が無ければ、民主的な Web 社会は保証されないのか?
以上がおいらができうる限りの匿名擁護論。以下は匿名マンセーな方々には少々厳しいお話。
上記で挙げたいくつかの例は、日本では割とありふれた感情だと書いた。それでも地域や年代などによって程度差はあるのではないかと思う。そして海外ではこの価値観は必ずしも通用するものではないとも思う。
おいらは一部の「匿名性が確保されているからこそ、立場を気にせず言いたいことを言い合える、真の民主的な世界が保証される」とした意見には到底賛成できない。
そもそも、自らの名も、立場も隠さなければ、言いたい事も言えない様な社会が、民主的であるといえるのか!!?? 根底の社会が民主的であるとはいえない状況であることを捨て置き、匿名の傘に隠れて不毛な愚痴や悪口や陰謀論などをぶちまけてガス抜きで満足しているような連中が、「ネットがこの腐った社会を根底から裏返した」などと笑止千万、寝言は寝て言えという話である。
最近、おいらはブログのページ右上辺りに、自らのプロフィールとして、本名と職業を公表するようにした。自分がこのブログ上で行う言論を評価していただくうえで、必要な情報であると (今頃になって) 理解したからだ。
例えば、8月の頭に、おいらは今勤めている職場内で起こった出来事について愚痴を書いた。このとき、おいらは勤め先がどこなのかまでは明かしては居なかったし、当時はプロフィールに本名も晒しては居なかった。
つまり、この時点で、たとえ当事者である職場の某氏がおいらのブログを読んでいたとして、それは彼にとっては知らないどこかの誰かが、別の知らないどこかの誰かのことを指して書いていることだと捉えるわけである。もちろん、会話の内容について事細かに書いているわけで、実際には自分のことだと既に察している可能性もある。しかし、社名が公表されていない以上、おおっぴらに何らかの対処を施す必要性の無い案件である、ということになるわけだ。
ところが、その後、8月下旬に、会社にクジラ飛行机さんがやってきて勉強会が行われ、それに感激したおいらが勉強会の内容をログに起こし、その中で勤め先の社名が OPTiM であることを公表したことで、事態は一変するわけである (しかも概ね時を同じくしておいらはプロフィールに本名を晒し始めた、確か)。これにより、つい先日に愚痴られた当事者の某氏は、その愚痴の内容が、自分の良く知る人間によって、自分に向けられて発せられた言葉であることを理解することを余儀なくされるわけである。しかも社名は公表され、おいらと彼の二人だけの問題では済まなくなってしまった。
民主的社会の議論の場においては、この、当事者を特定し、議論の場に引っ張り出すという過程が、どうしても不可欠なのである。そうでなければ、問題が報告された際、それを正すべき責任の所在が明確でないために、結局誰もその問題を正そうとはせず、状況は何も改善しない。問題解決につながらない議論になど、遊び以上の意味はないのだ。
逆に、自らの立場を明かし、当事者を明かすという行為は、自らの立場を守るためにも必要なことだ。もしも匿名で、自分と当事者にだけ分かるような書き方でしか書かなかった場合、その言論に感づいた当事者が、何らかの圧力をかけ、結果としてその愚痴を書いた人間が職を追われる、という事態にも発展しかねないが、そうなった後になって慌てて名を明かして俺はこんなことを書いたぐらいであの会社を辞めさせられたんだーなんてわめき散らしたところで、その経緯を証明してくれる人は誰一人居ないだろう。しかし、はじめから自らの実名を明かし、自分と当事者の働く会社の社名を明らかにすれば、不当に圧力をかけて辞めさせるようなことをすればそれこそ社名に傷がつく、という状況で、会社としても迂闊な行動には取れないということになる。多くの部外者 (そして潜在的な消費者) の衆目に晒された状態で、概ね対等の、解決に向けた本当に建設的な議論を期待することができる。
もちろん、おいらが書いた愚痴なんて本当に些細なことで、会社にとっても何の痛手にもなっては居ないし、そもそもこんな話に衆目が盛り上がって会社の名が傷つけられるような事態をおいらも望んでいるわけじゃない。何気に大した技術者たちがそこにこぞって集まっているのも事実だし (だからこそ、体は大切にして欲しいと願ったりもするわけだけれども)、そんな技術者たちをいい意味で刺激するイベントも結構あったりして、そういう意味でもとてもいい会社だと思ってる。ってちょっと話が逸れてきたな。
とにかく、実名でものを書いても事態は何も変わらないかもしれないが、少なくとも匿名で書かれたものに比べれば、実名で書かれたものが当事者に与える影響は確実に大きいのは確かだ。実名での言論は事態を変える可能性を孕む。匿名での言論は、本当にガス抜きにしかならないよ。何の解決も生まないよ。
本当の情報革命は本当の民主主義社会にのみ訪れる
池田信夫さんは上記でリンクした記事以外にも、こんな記事を執筆されている。こちらは非常に興味深く読ませていただいたが、氏の言う「本当の情報革命」が将来起こるのだとすれば、その土壌には、堂々と名を明かし、身分を明かしたものが形成する本当の民主主義社会の存在が絶対条件となるのではないかと思う。そうでなければ、共有される情報に対価の認められるような世界は、訪れる余地も無いからだ。


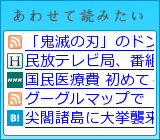





最近のコメント