blogosphere は「新しい知識人」の代替となりうるか? ― 2007年12月24日 14時37分31秒
全体性を知らないエキスパートからは「善意のマッドサイエンティスト」が多数生まれます。自分が開発したものが社会的文脈が変わったときにどう機能し得るかに鈍感なエキスパートが、条件次第では社会に否定的な帰結をもたらす技術をどんどん開発していきます。
バイオの領域でもIT(情報通信)の領域でも、人間であることと人間でないこととの境界線を脅かすような研究が進みつつあります。そうした社会であればこそ、社会的全体性を参照できるような知識人、私の言葉でいえば「新しい知識人」が必要となるわけです。
新しい知識人は、大衆を導くというかつての課題とは違った課題に取り組む存在です。エキスパートが社会的全体性を弁えないがゆえに「暴走」してしまう可能性を、事前に抑止するような役割を果たす存在です。そうした存在がこれからますます要求されるべきです。
欧米のノーベル賞級の学者の多くは、大衆向けで分かりやすいものの、極めてレベルの高い啓蒙書を書けます。知識人には専門性を噛み砕いて喋る能力が必須です。そうした能力は公的なものです。日本にそういう学者が数少ないのは、知識人がいないことに関連します。
これを読んでみて思ったのが、blogosphere が、宮台氏の言う「新しい知識人」の代替となりうる可能性についてです。大学に足場を置いた学問の世界では専門外の分野との繋がりが疎遠になりがち (そもそもそれが駄目なんじゃ、という気もしますが。。。) なのに対して、blogosphere には専門の異なるエキスパート同士の交流と議論がありうるからです。
もちろん、そうなるためには、blogosphere に参加する多くの人が、「新しい知識人」を目指すことが前提に無ければならないのかもしれません。今はまだ、専門の異なる者同士の見識の断絶が、有益な議論を阻害しているように感じています。例えば、Winny の違法性を巡る裁判および判決に対しては、専門の違いによって以下のように見識が割れました。
- Winny 自体は何ら法に抵触しないとしながら、金子氏のとった態度への評価として実刑が下された判決であり、今後の開発に不安を覚える。(プログラマー)
- 金子氏の行動が社会的に及ぼした影響と、氏の態度を考慮すれば、この量刑は妥当な手打ちであると言える。(法学者)
- 著作権よりも、ひとたび流出した「秘匿すべき情報」が回収できないような仕組みになっていること自体が重大であり、そのことに対して新たな法的枠組みを早急に作るべきだ。(セキュリティ研究者)
まぁ、3つ目は当の裁判とは直接の関係は無かったわけですが。。。
上記の 1 と 2 は、相容れない意見として最後まで断絶していたように思います。1 の意見に固執するプログラマーには、技術が時としてもたらす無制限の損失の可能性に対して、法的手打ちを欲する (あるいは必要とする) 権利者という社会的構図に対する理解が足りなかったし、2 の意見に固執する法学者には、有益なソフトウェアを発明し、開発する個人プログラマーが、法的リスクに尻込みすることで技術的発展が損なわれる可能性に対する理解が足りなかった。
これらの双方が歩み寄って足りない理解を補い合うことで、より有益な議論を導き出すことができたのではないかと思うんですよね。個人的なソフトウェア開発が法的リスクに晒されるのは恐い。でも、なんでもありの個人開発を法的に放置することによって、具体的な損害を蒙る人が出るような事態は避けるべきだ。ならば、双方を満足するようなより高度な解決策は何なのか。そこに法的不備の可能性は無いのか? かといって、ad hoc な法の調整で事足りる問題なのか? 等々。
こんな感じで、今はオタクでしかない各分野のエキスパートたちが、議論の場としての blogosphere を通じて、「新しい知識人」的な、即ち横断的な知識の共有と蓄積を繰り返していけると良いのではないか、と思いました。
コメント
トラックバック
このエントリのトラックバックURL: http://harapeko.asablo.jp/blog/2007/12/24/2527282/tb
※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。


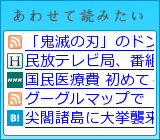





コメントをどうぞ
※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。
※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。