ほっとけない in 千葉大学 ― 2006年04月30日 00時40分10秒
2006年04月21日 千葉大「ホワイトバンド」講義、規模を拡大して開催
2006年04月28日 千葉大講義・第3回「アフリカの今と日本の私たちのかかわり」
(いずれも、ほっとけない 世界の貧しさキャンペーン内のキャンペーンニュースより
本題に触れる前に一応おいらの立ち位置について再確認。おいらはこのキャンペーンに賛同する意思を持って、白いものを体に身につけたことはないし、今のところ、自分がそのような意思を持つ可能性は低いと思っています。
しかしながら、そんじょそこらのホワイトバンド賛同者などよりは、よっぽどこの市民活動に対して関心を寄せている自信はあります。いや、ごめんなさい。ぜんぜん不勉強なんですけどね。(←弱っ)
さて、千葉大にて講義という形で行われているこの活動、なかなか興味深いので取り上げさせて頂きました。次回お忍びで見に行ってこようかなぁ(とかゆ)。
以下は第3回の講義内容より引用。
「(中略…)エイズは、新薬の登場で、死ぬ病気ではなくなってきたが、高い薬を買えない途上国の子どもたちは死んでいる。薬が高いのは特許、知的所有権によって発明者が特別な利益を得るしくみのため。命を尊重するのか、知的所有権という経済的な権利を尊重するのか。この問題が裁判になったとき、日本は知的所有権を重視した国のひとつだった。この裁判は、初めほとんどの関心を持たれなかったが、エイズ患者みずからが法廷に立ったことや、命の尊重を選ぶことを意志表示した人々がたくさん現れたことで国際的な関心が高まった。そして、裁判官は命の尊重を選ぶ判決をくだした。(…中略)」
背景については、例えばこの辺なんかを当たってみるとわかりやすいかも。情報量ではこの辺が多いけど、これを全部追っていくのはさすがに大変かな。キーワードは、「ドーハ宣言」と「TRIPS」。より関心を高めたいのであれば、これとかこれなんかも目を通してみると良いかと。
しかし知的財産権が人命保護への足枷になるという観点はなかなか重要なものだと思う。個人的には、関連して容易に思い出されるのが、著作権とデジタルメディアの関係だったり、特許とソフトウェア技術の関係だったりするわけですが。知的財産権の多くは、本来弱者に保障されるべき権利の一部ないし全てを犠牲にして成り立っているんだなぁなんて。
さて。以下は単なるイヤミだ。
まずは、第2回の講義内容より引用してみる。
ホワイトバンドはつけるだけで終わりじゃない。
前振りは前振りでしかないと思うのでばっさりカット \(^O^)/ 。
おいらが白いものを (ホワイトバンドキャンペーンへの賛同の意を示す目的で) 身に着けることをしない理由について、ここで一度述べておこうと思う。
市民活動と言うものは、本来、立ち上げの意思に対する賛否を問う前に、先ず参加の意思を示し、その上で、各自が意見をぶつけ合うことによって、活動全体が成熟してゆくものであるべきだ。重要なのは以下の 3 つ。
- テーマが明確であること。
- 参加者がテーマに関心を寄せていること。
- 参加者がテーマに関して積極的に議論を交わすこと。
1 は達成されている。日本では不明確だったのはお金の流れの話であって、テーマ自体は決して不明瞭だったわけではない。あくまでテーマは「貧困問題」である。もっとも、Live8 がキャンペーンの大元であり、関心の対象が主にアフリカであると言う点が十分周知されていたかは確かに微妙なところではあるが。
そして、問題は 2 と 3 にある。確かに、キャンペーンの存在自体については、一時的にではあるが関心が寄せられたのは事実である。しかしその関心は、あくまでキャンペーンの華やかさ、ファッション性に対するものが中心で、もちろん、「1秒に 3 人の子供が死んでいる」→「かわいそう」という思考論理で関心を寄せた方も多くいらっさったのも事実だが、それはあくまで「1秒に 3 人の子供が死んでいる」という出来事に対する関心でしかなく、キャンペーン自体の方向性や、関係する事務局、代理店、NGO の活動や、その後の社会的な動向に対する関心にまでは繋がっていないのが現状ではないか。
そして、こうした肝心の「関心」と「議論」について、ホワイトバンドキャンペーンの (特に、日本の「ほっとけない」キャンペーンの) やり方では、市民活動として定着してゆくことはなさそうだ、という空気を感じ続ける限り、おいらはどうしてもこのキャンペーンに賛同の意を示す気にはなれないのである。
活動の趣旨、具体的な方向性に対して、賛同できるか否かは、この市民活動に参加すべきか否かを決める基準としては、実は重要ではない。何故なら、その方向性に問題があると思うならば、むしろ参加して、自分が声を上げることによって、その方向性を修正するよう努めるべきだからだ。でも、そもそもキャンペーン自体が市民活動としての成熟を望んでいるように見えない状況で、そこに市民としてどうコミットのしようがあるのだろうか。
以前、ザンビア政府の対応がホワイトバンドを支持するブロガーの間でちっとも話題にされていないということを書いたが、今回千葉大学にて行われている講義についても、ご多分に漏れず、ほとんど話題にされていないようである。今回はテクノラティに限らず、ブログ検索に対応したいくつかの検索サイトにて、「ホワイトバンド 千葉大」で検索した現時点の結果を ウェブ魚拓にしたものを、以下に示す。
関連する記事として引っ掛かるのは、あたしのき・も・ち さまと、coccoloのdiary さま、そして紹介している大本営記事だけなのである。あまりにも語られなさ過ぎだ。
ただ、そうした中で、とりわけ今回の千葉大での講義については、珍しくまともな活動、すなわち光明なのではないかと思うのだ。
「ほっとけない」のこれまでのキャンペーン行動は、ファッション性や派手さ、著名人を利用した抜群の広告力によって、力ずくで効率的に多くの人に周知する方法を採ってきた。その結果として、本質的な問題への関心は一過性に終わり、キャンペーンは現在、振り出しに戻っている状態、と言えるのではないかと思う。
今回、大学での講義という形を取ることによって、限られた人数ではあるが、本質的な内容について、十分に時間をかけて語り合う場を設けている。これは、キャンペーンを推進する事務局において、大きな進歩であると思う。
願わくば、同様の進歩を、参加 NGO も、それからホワイトバンドを身に着けるという形で支持し、参加している市民たちも、遂げるべきだ。それが為されるのであれば、キャンペーン立ち上げ時の、カネに関する疑惑など、些細な問題と言い切ってしまってもさしたる問題ではあるまい。
更に言うならば、かつて「ほっとけない」キャンペーンに対して強い疑惑や不支持を示していた方々 (敢えて名指しをするならば、まとめサイトなどを作っていた 2 ちゃんねる界隈の方々とか、かつて「ホワイトバンド撲滅キャンペーン」を敷いていたはずの毒電波TV さま、それからうちにも tb を送ってくださっていた、かなり詳細に突っ込み入れまくっていらっさったハズの水谷まちこのSPAM大好き! さま、他にも有名どころの blog で疑惑を展開させていたところは相当あったハズだし、一部マスコミも当然含む) についても、同様のことが言えると思うのだ。本気で疑惑を追いかけるつもりがあるならば、彼らは今でも疑惑を追い続けているべきだし、その為には現在の「ほっとけない」周辺の動きについては注目し、話題として積極的に取り上げてゆくべきだった。
結局、キャンペーンそのものがファッションならば、それに対する批判でさえもまた、ファッションに過ぎなかったのだ。こういうことが繰り返されるにつれ、つくづく、この国にはジャーナリズムは存在しないのだと嘆いてしまうのである。


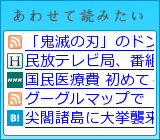





最近のコメント