RFID で児童の仲良し分布をチェック ― 2006年08月17日 07時26分03秒
とりあえず、紹介されている CE の記事を読んで、ちょっとだけ安心した。今の世も、多くの子どもは至ってまともだ。
正直言って私の感覚では、この発想はクレイジーだと思う。しかし、根拠を持って批判する術はない。主観的な感想でしかない。人々はこれをどのように受け止めるのだろうか。
クレイジーです、間違いなく。
おいらは、すべての人間が友達を持っている必要は無いと思っています。っと、これはやや極端な言い方なのですが、もうちょっと砕くと、人付き合いの形というのは、人それぞれでいい、ということです。
人間、生きていると、人付き合いよりも重要なものを見つけてしまったりすることも多分にあるものです。例えば、本を読むことの楽しさを知ってしまった子が、授業が終わると誰よりも早く教室を飛び出し、家に帰るとすぐ、町の図書館へと足を運ぶようになったとします。RFID システムにより、この子だけが、他のどの子とも連続せずに、真っ先に帰宅していることが把握されます。教職員会議にかけられ、教頭辺りにこの子の交友関係改善を、担任の教師が命ぜられたりします。仕方がないので教師がこの子に掛け合い、説得したりします。さて、この子はどう思うでしょうか? あるいは、この出来事を周囲で見守るクラスメートは、どう思うでしょうか?
人様の交友関係についてとやかく言われることほど、不愉快なものはありません。今の学校教育がそれを実践しているのだとすれば、それは狂っているとしか言いようの無いものです。教師になど言われなくたって、子どもたちは勝手に独自の交友関係を築いています。逆に、交友関係を上手く築くことのできない子は、教師がそこに口を差し挟んだところで改善されるものでもありません。それどころか、「友達がいないのは異常である」というような認識を子どもに植え付けること自体が非常に危険なことです。友達がいない人間は、必ずしも犯罪予備軍なのでしょうか? 友達さえいれば、人間は犯罪を犯すことは無いのでしょうか? 友達がいなくても健やかに日々を過ごすことのできるタイプの人間は確実にいるのです。「友達がいないのは異常」という認識が広まれば、友達を作らないタイプの子どもはますます子ども社会から疎外されてゆくことでしょう。
ひとつ批判的な議論が可能なのは、校門を同時に出入りすると仲良しと見なされるようになっていることを、児童たちが知らされるかどうかという点だろう。
(中略)
この考え方の延長だと、校門の出入り記録を仲良しの判定に使うことは児童には知らせないのだろうか。
それを事前に児童たちに知らせた場合は、何が起きるだろうか。あるいは、知らせないで運用したときに、ある日、児童たちがそのことに気づき始めた場合、児童たちはどんなことを思うのだろうか。
知らせるだけじゃ駄目だよ。拒否権を与えて初めて「フェアである」と言える。知らせりゃいいってもんじゃない。「仲良しチェックしますから」っつって、嫌がる子どもがいたって、結局はチェックするんでしょ? それじゃあ意味は無いよ。
コメント
_ @DRK ― 2006/08/17 14:16:27
_ T.MURACHI ― 2006/08/17 17:02:21
彼らがやりたいのは「調査」というより、どちらかと言うと「監視」だと思う。だから高木氏は「知らせる必要がある」っつってるワケで。
おいらとしては教育の現場でこのての監視を強化しようとする場合に、子どもに正当な拒否権が与えられることは無いだろうと思うので、そういう調査を行うこと自体に反対なわけだが (そもそも教育現場への RFID 導入自体反対だけどね)。
_ @DRK ― 2006/08/17 19:16:55
だとしても、監視する、という情報は子供に伝わって素の行動を阻害するだろうし、そんな状況を監視してどーすんのかな、と思うが・・・そんな状況下だとますます友達いない子供は浮き彫りになるから、むしろ好都合なのか。
そこまで考えてないと思うけど。
そもそも校門通過記録だけで調べようとしてるのがおかしい。塀を乗り越えた児童はどーすんだ。
_ @DRK ― 2006/08/17 19:20:13
>学校は生活のリズムの中にあるごく普通の場所で、
>自宅にいるのと同じような感覚で過ごせる場所にしなければならないと思っています。
こんなこと言ってる先生だからこそこんなクレイジーシステムを考えるんだろうか。
アホか。
_ 半日庵 ― 2006/08/17 23:30:01
私はこの教師は随分と狭い視野しか持っていないと感じます。きっと学校の外のことは何も知らないのでしょう。なにも友達は同じ学校にいるとは限りません。塾やスポーツクラブ、保育園がおなじった隣の学校というのもあります。
_ T.MURACHI ― 2006/08/18 16:34:53
まぁ学校って場所の捉え方については人それぞれでいいとは思うが、自宅と同じような感覚で過ごせる場所にしたいなら、余計な詮索・干渉はするべきじゃないよな。家庭では親に干渉されて窮屈さを感じて居場所を失い、学校では教師がシステムバリバリ使って干渉してまた窮屈さを感じて居場所を失い、そうして自らを追い詰めるタイプの子どもはどこへ行ってしまうのだろうね。もっとも「自らを追い詰めるタイプ」って、いまどき子どもに限らない話だけれども。(←話逸れてる逸れてる^_^;)
>半日庵さま
この教師のことについて想像で書き立てるのは「まだ」止めておきませう。ブログを持ち、市井の声を聞く姿勢が少なからずある。それだけでも、まだまだまともな方だと思っています。
この教師は、ブログ上での発言を見る限り、どうやらいじめ問題などは教師ががんばって防がなきゃあかんもんだと考えているようです。社会情勢などに不安を感じている節があり、将来的に、子どもの交友関係などをできうる限り把握できる体制が必要になるかも知れんと書いています。
半日庵さまのブログ記事を拝見しましたが、半日庵さまはこの教師について、「生徒の生活を把握していない」と書かれていますが、おいらとしては、そもそもそれは教師の仕事では無いし、学校法人の責任でも無いと思っています。子どもの親たちは学校という場所を、子どもに社会性を身に付けさせるために「利用」しているかもしれませんが、学校というシステムの命題は必ずしもそこにあるわけでは無いでしょう。
教師は教育に専念すべきである。まったくその通りであるとおいらも思います。さればこそ、児童・生徒間で起こった交友関係上のトラブルについてまで、教師が責任を負わなければならないという約束事を、法的にも契約的にも社会通念的認識においてさえも持たせるべきではありません。
もちろん、教師が子どもにとって「親以外の大人の人」として子どもと接する上において、子どもたちが抱えている交友上の問題について相談を受け、その信頼を以って真摯に接し対応すること事態は素晴らしいことであり、それはもう「教師だから」とかなんとか言わんで一人の大人の人間として遂行してあげて欲しいなぁとは思うわけですが。幸いにも教師っていう職業はそういう場面に立ち会う機会の最も多い職種ではあるわけで。(但し義務であってはならないけれども)
大体マスメディアも教職をいぢめ過ぎなんだよな。いじめ問題然り、体罰問題然り。
そもそも子どものいじめを否定するなら、もとより現状の学校なんていうシステム自体を否定せにゃならんワケですよ、ってこれは「大人問題」での五味氏のウケウリ。
_ 半日庵 ― 2006/08/22 22:02:45
私のブログは教師の力量という面で書いています。ただ義務とか責任とかに関してあまり考えずに書いてしまったので、その面から見ると曖昧と言うか考えが足りない部分があるようです。
私は小学生のころいじめられっ子でした。その時の体験から教師にも生徒の中に入り込んだ教育をしてもらいたいと思っています。それが出来ていなようでは教師としての力量が十分ではないと考えています。現状そのようなところまで望むのはちょっと高望みかもしれませんが、願望として、そんな教師こそが評価されてほしいというものがあります。
コメントをどうぞ
※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。
※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。
トラックバック
このエントリのトラックバックURL: http://harapeko.asablo.jp/blog/2006/08/17/486877/tb
※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。
_ パパのインターネット巡回生活 - 2006/08/22 02:18:18
正直言って私の感覚では、この発想はクレイジー
だと思う。しかし、根拠を持って批判する術はない。
主観的な感想でしかない。人々はこれをどのよう
に受け止めるのだろうか。
出典(部分引用):http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20060813.html#t
高木浩光
これに対しての私の結論は「学校、特に小学校は
そういう管理をしたがる所だから、そう考えて普通じゃない?
何が変?」ということかな。実際、先生と家庭訪問やら面接
で話せば、交友関係は細かくみていることがわかる。
たぶん生徒管理の基本なんだろうね。RFIDタグが有ろうが
無かろうが、そういう視点でみているものだがら、下校時の
人間関係という分析要素が加わったことを大げさに驚く
方が驚く。そういうのを理解してないでセンシティブに対応
するのは、たぶん木を見て森を見ないことなんだろうね。
音声とか画像とかの詳細なログまでになったらどうかと
思うが、これとて、校内の犯罪が仮に深刻になればしょう
がない気もするし、子供の位置情報位なら、親としてしょ
うがないと思える範囲と思うけどね。逆に先生にとっても
その程度では、それほどの価値のある情報では無い気もす
る。


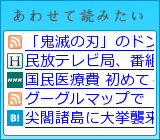





この調査がどこまで信憑性があるのか、甚だ疑問です。
サイスンスの基本中の基本だけど、観測者が観測系に影響してはいけないのですよ。というか影響したらそもそも調査の意味がない。
(経済学方面ではそれを踏まえたうえでの考察になっているよーだけど)
子供に「調査する」と知らせればその時点で生の子供の行動じゃなくなる。それじゃあデータとしてあかんわな。
そんなアバウトな実験調査で子供のプライバシーを侵害しまくる必要など一切なし。タグだけ捨てちまえw