住基ネットとプライバシー ― 2007年03月01日 09時43分51秒
週刊ミヤダイ 2006/12/1 更新分に関するメモ。
- 話題はこのニュース。。。ではなくてw、その元となった裁判の判決に関するもの。
- 前提 - 社会が情報化した→電子政府化構想。行政コスト低減を目的とした個人情報の集約。勝手な扱いを避けるため←個人情報保護法。
- 前提 - 各行政機関、学校、病院、民間業者などにおいて、独自に個人情報の蓄積を行っている。
- 住基カードのテクノロジーだけが高いセキュリティを確保していても、住基ネット全体に関わる人間全体をコントロールできるような枠組みが無ければ意味が無い。
- 電子化により、データの結合が可能になった。住基ネット番号だけで (~さえ暴けば)、個人の多くの属性情報を紐付けて引き出すことができるようになる。
- プライバシー権とは、自己情報制御権、すなわち「自分がどういう人間であると見せたいかをコントロールする権利」のことを言う。「見せたい自分を見せる権利」、「見せたくない自分を見せなくてもよい」という権利。
- ex1) 和食の達人と呼ばれる人の家を訪ねたら、洋食の食材、食器しかなく、普段和食を食べていないことがばれてしまう→言いふらされる (住居不可侵を破られることによる被害の例)
- ex2) 市民が政府にクレームをつけるときに、クレームに対する反抗として、恐喝の材料に悪用される可能性→政府に異論が言えなくなってしまう (住基ネットが行政においてデータ結合可能な状況にあることの脅威に関する説明)
- ex3) アメリカにおけるレイプ裁判 - 「被告人は○○のような性的な放蕩に耽っていた」とする証言は昔はよくあったが、違法となった←「尊厳の剥奪」(過去は過去として現在はこう生きている、と見せたい自分を破壊される) となり、社会生活を送るための根本の基盤が崩れてしまうのを防ぐ為。
- 抜き出したプライバシー情報を用いた恫喝等を罰する法律は個々に存在するが、それだけでは不十分。データ結合自体を違法とし、重罰化する必要がある。
- 「見せたくない過去」とは、必ずしも違法行為のことではない。様々な価値観があり、さまざまな場面において、自己呈示において見せたい自分、見せたくない自分が存在するのはごく自然なことである。
- 政治家は公人。ジャーナリストは制限された公人。公人にはプライバシー権は認められない。制限された公人にも、当該専門分野に関わるプライバシー権は認められない。←日本ではこの辺の常識がいまいち定着していない。
- 後半は Web サービスや ETC、RFID などに関わるデータの蓄積と、個人の追跡可能性に関するお話。
- 自己情報アクセス権 - 機械が勝手に収集した情報の蓄積を参照する、あるいはどのような基準で情報の収集が行われているのかを知る権利。
- 情報の蓄積による追跡可能性は問題かもしれないが、一方で便利なものでもあり、便利さには変えられない、という側面もある。
- 自分で選択できるのが良い社会である←機械が蓄積した情報に基づいて物事の (限定された、オススメの) 選択肢を用意する (選択肢が結果的に狭められている)。
- 学校のクラスで名簿が作れなくなる、というのは個人情報保護法の観点では間違い。但し、「名簿に載せてほしくない」という個人がいるのであれば、その個人の意思は尊重せざるを得ないだろう。
- 社会生活を送る以上必要最低限の情報は絶えず公に晒して生きるしかない、ということが忘れられがちになってきているのでは? ex) 連絡を取り合う必要がある以上、連絡先の情報は共有せざるを得ないはず。→自己情報制御権の乱用 (個人情報保護法施工の弊害)
- 近代社会の前提: 「知らない人は、信頼できる」 ex) 知らない人と同じ電車・バスに乗れるのは何故か。知らない人が経営するレストランの、知らない人が作る料理を食べられるのは何故か。
- 1970年代、上記前提に対する不安が流行した。ex) ミミズ肉バーガー、猫肉バーガー等の都市伝説 →現代では克服されたはずの概念。
- 「知らない人は信頼できない」という前提の社会は、生き方として健康ではないのでは? ex) 「誰も人を殺してはいけないとは思っていないが、監視ネットワークが発達したおかげで誰一人殺されない社会」と、「多少の人殺しはあるけれども、社会の大半の人間は心から人を殺してはいけないと思っている社会」、どっちの方がよい社会か。現状ではどうやら前者を目指しているようだが?
コメント
トラックバック
このエントリのトラックバックURL: http://harapeko.asablo.jp/blog/2007/03/01/1217602/tb
※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。


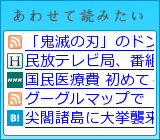





コメントをどうぞ
※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。
※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。