宋文洲×浅野史郎対談 ― 2007年03月04日 09時05分15秒
面白い。宋氏の生い立ちに関する話題に絡めて、外国人だからどうのこうのなんてことは無いよという話や、日本の営業マンの常識は世界の非常識みたいな話、それから生い立ちとは離れて、夕張の財政破綻や、子どものいじめ問題、格差社会、そして日中関係についてまで言及している。
浅野 誰だか知らない留学生の中国人がコンピュータの計算ソフトを待って行ったら、みんなびっくりしたでしょう。
宋 それが不思議なんだよ、日本は。バンバン売れるわけ。普通、外国人は日本に入りにくいというけれど、それがわからないから、こっちもどんどん営業する。
浅野 何も知らなかったのが、かえってよかったんだ。
宋 だから外国人だからどうのこうのじゃなくて、ルートさえちゃんと見つければ大丈夫。レベルの低いやつに限って、外国人はどうのこうのと言うわけよ。
なるほど。先入観に囚われずに行動できるってのは、素晴らしい事だよなぁ。。。
宋 そう。ところが営業マンを雇ってみたら、やつらはさっぱり売れないわけね。それで気付いたんです。「そうか、日本の売り方はこれだからダメなんだ」と。そこで実際に日本の営業はどういうものかを調べていくと、かなり変な売り方をしている。せっかく売れるものも売れないわけよ。まず気付いたのは接待の嵐。今はだいぶよくなったけれど、当時は何でも接待から始まる。宴会、カラオケ、ゴルフ……。中身も説明しないで「買ってください」と言い出すんだよね。それじゃあ、いいものと悪いものの区別がつかない。だから権威で物を売ろうとするし、大手の会社じゃないと売れないということにもなる。正直に言うと、そんなことでは経済はおかしくなるんだよ。何でも権威だけで動いていたら、本物はなくなってしまう。僕はおかしいと思って、途中から、そうか、これなら「営業を改革するような商売」のほうが儲かりそうだ、と思ったんですね。営業をやっていない会社はないわけですから市場も大きいはずだ、と。
今だって、売る人間が何を売っているのかわかっていないような状況ってのは結構あるけどね。「技術営業」を謳っている会社であってもそうだったりするし。。。商学を学んできたものでなければ営業は勤まらない、とか、物を売るまでのプロセスにおける「物を作る」って部分と「売る」っていう部分が、まるで別個の相容れないスキルである、みたいな固定観念が、どちらかというと現場レベルというか労働者側に蔓延っているような気がする。営業をやりたがらない技術者も多いし。
芸術系では既にある動きだったりもするんだけれども、今後は技術系・工学系であっても、自分で作ったものをいかにして売り込むか、っていうことを学ぶ機会を得ることは、重要だと思う。
浅野 根性だ、気合だ、接待だ、という営業ではない正しい営業というのは、どういうことですか。
宋 それは浅野さんがいま答えを言ったんですよ。ライトパースン、ライトタイム。つまり、相手がほしくないものは売ったって意味がない。誰がほしいかと言えば、ライトパースンですよ。いつほしいか。ライトタイムでしょう?
要は、自分が売ろうとしているものを欲しがる人を徹底的に探せ、っちゅーことだわね。もちろん、欲しがる人が多そうなものを商品として用意できなきゃあかんわけだけれども。
宋 子どもの自殺の問題ですが、僕の見方はマスコミと違います。これは政府の問題でもなく、学校の問題でもなく、子どもの問題でもないと思う。大人は子どもに対して、無条件にとにかく友達と仲良くしなさい、という要求がきついんですよ。人間社会というのは、仲良くできない部分もあると思うんです。友達と仲良くできない場合は、無理せずに転校すればいいんだよ。
(中略)
宋 逃げ場があれば誰も自殺しません。こんなに子どもが自殺するなんて、あり得ない話だよ。それは親が逃げ道を教えていないから。多様化とか何とか言うけれど、目本の教育は多様化なんかじゃないよ。要は村八分しか教えていない。
まず親は、「お友達と仲良くしなさい」なんて教えないこと。いやなお友達とは付き合うな、と。周りの四人、五人から悪いことをされたら、「五人とも悪くてあなただけが正しい可能性があるんだよ」と親は教えなくちゃ。
中国は歴史的にパトリの概念が薄い (土地に縛られない)、血縁ネットワークを重視する社会だったりするので、宋氏の上記のような考えはある意味で中華的だと思う。そういう意味で批判する人はいるかもしれないけど、でも、おいらは上記の考えに概ね賛成。
ただ、中長期的には、わざわざ引っ越さなくても逃げ場は他に提供されるような社会であって欲しいし、あるいは引っ越すという行為に抵抗感が強くなくなるような社会でもあって欲しいと思う。皮肉にも、住基ネットが行政処理上は引越しを容易にする仕組みを提供するシステムとして機能しているわけだけれども、重要なのはそういうことではなくて (^_^; 、いろんな形でコミュニケーションの為の受け皿が地域ごとに提供されること、地域がそういう受け皿を提供しやすくなるような制度が作られること、なんではないかと思う。
宋 あれは絶対、偽善。終身雇用は社員のためにならないと思う。社員がソフトブレーンを気に入って結果的に死ぬまで勤めてくれたら、それはソフトブレーンがすごいのであって、とにかく社員を囲んで「おまえ、やめるのは裏切り行為だぜ」なんて言うのはおかしい。
だいたい、正社員も三年ごと、五年ごとなど契約制にしたらいいんですよ。目本では会社で正社員として働くとき、契約書を交わさないでしょう。これも本当はおかしい。
正社員も契約制か。雇用主と労働者の立場が対等でなければならないと考えれば、確かにそうあるべきだよなぁ。労働者には働く場所を選ぶ権利があるし、雇用主にも労働者を評価する権利がある。
浅野 結婚もそうですか。やっぱり流動的に?(笑)。
宋 もうちょっと不幸な結婚を維持しないような国になれば、日本の出生率は高くなるよ。
浅野 たしかに不幸な結婚を続けるよりは、幸福な離婚をしたほうがいいですね。
社会制度として内縁を事実婚に認めて待遇しているのはフランスだったっけ? 制度の良し悪しは別としても、社会的にはその方が「成熟している」とは言えるわね。
浅野 僕がいまいちばん気になるのは、同じような仕事をしながら、たまたま正社員として遇されるのと非正規雇用とでは、報酬や処遇がまったく違う。これはそのままにしてはおけない格差でしょう。
宋 僕も全く同じ見方です。ただし、その場合は「格差」とは言わない。これは「アンフェア」だと言っているんです。不公平なんです。しかも違法性がある。これは許せないと思う。格差じゃない、これはアンフェアですよ。
同意。ただ誤解があってはならないのは、派遣のような業態で仕事に臨むことを望む人もいるということ。だからこそ、正社員も三年ごと、五年ごとなど契約制にしたらいい
っていう意見には、頷ける。逆に、派遣社員や契約社員にも正社員と同等の社会保障的な待遇は保証されるべきと思う。もちろん、会社ごとの差はあっても仕方が無いと思うし、能力差が給与に反映されるのも仕方が無いと思うし (評価が正しく機能しているならね)、契約形態の違いに伴って仕事の内容も異なると言うのであればそれによる給与の差があってもやっぱり仕方が無いとは思う。
金銭的待遇の問題だけじゃない。こういう仕事があるよ、と言われてやってきた派遣スタッフが、実際には雑務しか割り振られず、その仕事内容に絶望する、というケースも少なくないんじゃないかと思う。逆に、仕事の内容を明示されてやってきた派遣スタッフに、自分で仕事を能動的に見つけることを要求する現場社員との折衝、なんてこともあったりする。雇用形態が違う割に、その一番の違いであるはずの「契約」が、守られないことを前提に打算で動いていたりすることが少なくない。そういう権力的暴力に、すべての労働者が強い態度を示せるわけではない。そして最後には「事なかれ主義」が作り出す空気がすべてを支配していたりする。一番駄目なのはそういう部分だと思う。
これまでの日中関係というのは、田中角栄さんや周恩来さんによって、ただ政治によって訴えられた日中友好から、だんだん政治と関係ない経済のレベルや文化のレベルで、隅々までお互いに絡み合ってくるようになってきました。政治の側が関係を悪くしようと思っても、なかなかできないような状況になってきました。それを、今回明らかに政治の側はもっと悪くしたかったんですよ。でも国民は、これ以上はもうやめてくれ、と。国民世論は政治に対してノーを言い出しているから、政治家も軌道修正をせざるを得ない。これは日中双方がそうなんだよ。
浅野 お互いがお互いを必要としているという関係が、経済的にも、もう後戻りできないくらいにできてしまったということですね。
宋 そうです。仲良くするいちばんの方法は、お互いの利益を、お互いが共有することです。口で言っているだけでは、やっぱり危ない。夫婦関係で言うと、子どもができたら離婚しにくいのと一緒よ。
現状の日中関係が不幸な結婚
であった、なんてことがありませんよーに。w
以上、記事の感想をこちらのブログ記事に tb としてお送りいたしまする。m(_ _)m
コメント
トラックバック
このエントリのトラックバックURL: http://harapeko.asablo.jp/blog/2007/03/04/1226907/tb
※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。


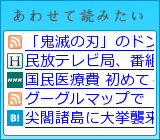





コメントをどうぞ
※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。
※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。