Blogger's accountability ― 2006年02月23日 10時30分45秒
そんな中、先日の電気用品安全法 SideAの記事に関して、こんなことを小寺さんがBlogで言っていた、という新しい解釈のBlog記述を発見して、衝撃を受けた。
すなわちパソコンのモニタ経由で見ている以上、それがニュースサイトの記事だったりコラムだったりBlogであったりというツールの使い分けというのは、あくまでも発信側の理屈であって、みる側としては信憑性も含めてなんもかんも一緒くたに見えているということなのである。
ジャーナリストではないブロガーであっても、発言には責任を持たなければならない、っていうのは、まさにこういうことを指して言うんだろうなと思う。読み手も人間であって、さまざまな捉え方をされる。中には当然、自分にとって都合の良い情報だけを集めるために、検索サイトを使い、引っかかった記事が新聞社のものであろうと出版社のものであろうと個人のブログであろうとも、お構い無しにそれらを根拠として物事を解釈しようとする人はいるわけで。
ブログなんて、通常は報酬を得て書いているものではないから (アフィリエイトによる間接的な収入は、記事を書いたという「仕事」に対する評価としての報酬ではないのでここでは論じません)、責任など発生しない、ブロガーが好きなように書けばいい、と捉えている人はたくさんいます。もちろん、その考え方もそれはそれで間違いではないと思います。ただ、仕事ではないとはいえ、最低でも、書いている内容が、不特定の人間の目に触れるものであることぐらいは、配慮している必要があるのではないでしょうか。
個人的には、以下の事ぐらいは配慮すべきなんではないかなぁとか思っていたりするわけですが。。。
- あからさまな嘘を、まことしやかに書かない。
- 情報の根拠を求められた場合には、可能な限り説明する。特に根拠がなければ「根拠はない」ということをはっきり明かす。
- 特定の人をむやみに中傷しない。
2 つ目は微妙かな。。。コメントもトラックバックもメールすらも受け付けないようなサイトを否定することになるからね。「推奨」ぐらいがちょうどいいのかも。
リーナス DRM 考 ― 2006年02月23日 11時25分49秒
「ライセンス」カテゴリが欲しいなぁ (^_^; 。つか、この記事に気付くの遅すぎた orz 。
DRMの実施を阻止したいと本気で考えるなら、それに相応しい行動をとるべきだと思います。興味深いコンテンツを作り、その「コンテンツ」について、暗号化や使用制限を禁じてください。
つまり、反DRM条項はCreative Commonsライセンスという文脈の中にある方が、ソフトウェア・ライセンスの中にあるよりも、ずっと意味があると私は考えるのです。人々が使いたくなるような価値ある有用なコンテンツ(覚えやすいメロディー、面白いアニメ、わかりやすいアイコン)を作り、いかなるコンテンツ保護の仕組みも適用してはならないと宣言することで、その「コンテンツ」を守るべきだと思います。
まったくもって同意。DRM もレコード会社も権利団体も気に食わないって人はつべこべ言わずに積極的に作品を作ってゆくべきだし、あるいはそうやって配布されている作品に対してもっとアンテナを張るべきだと思う。メディアに流され流行に流され、そうやって生きるのが楽チンでそれ以上を求めたくない人たちはどうぞ奮って無駄金はたいて生きていてください、ってこった。
つか、だれか同人専門通信カラオケ作ろうよ~(ぉぃ
たとえば、ディストリビュータが「自分で」コンパイルしたカーネル・モジュール(GPLの下で配布されているもの)に署名し、そのカーネルのロードを拒否する場合(「secure policy」)、あるいは、ロードは許すが「Tainted」とする場合(「less secure」ポリシー)、それは「よいこと」です。
GPLv3の現在の草案では、誰でもRed Hatが作った署名つきバイナリの自分用のバージョンを再作成できるようにするため、Red Hatの秘密鍵を配布し、再コンパイルしたモジュールに署名できるようにすると明記している点に注意してください。これは、とんでもない話です。
因みにお伺いしますが、署名つきRPMアーカイブについては、いかがお考えでしょうか。ディジタル署名が信用できない場合、安全な自動更新をどうやって実現させるのでしょうか。
スバラシイ。いや、当たり前のことか。むしろ GPL v3 草案作った連中はいったいどの程度ピアレビューを行ったんだと小一時間問い詰めたいくらいだ。
よーわからん、という人の為の拙い解説をば。Linux やそれに付随する GNU ツール等々は、大元では生のソースコードで配布されているわけだけんども、Red Hat や Fedora Core 、Susie、Vine みたいな多くのディストリビューションパッケージでは、インストールを手早くできるように、あらかじめコンパイルしておいたバイナリコードで配布していたりする。まぁ、よーするに Windows と同じようなことやってるわけやね。
んで、これまた Windows と同じようなことなんだけれども、Linux といえどもやっぱりセキュリティー上の問題というのは日々発生するわけで、欠陥が見つかればその都度修正し、修正した部分のパッチを配布しなければならないわけだ。これが生のソースコードを元に自分でコンパイルして突っ込んだ人ならば、更新されたソースコードを拾ってきて自分でコンパイルしなおしすればいいわけだけれども、そうではなくて、上で挙げたようなディストリビューションを使っている人は、パッチとしてあらかじめコンパイルされたバイナリをもらって、そのバイナリをインストールする、という方法になる。Windows Update と同じやね。
Windows Update にせよ、Linux のパッチにせよ、配布されてきたものが、本当に正しいパッチなのかどうかが確認できる必要がある。正しいパッチというのは、すなわち、本来そのパッチを配布すべき人が製作したパッチなのかどうか、ということだ。Windows ならばそれは Microsoft が製作したものでなければならないし、Linux ならば、使用しているディストリビューションを開発・配布しているディストリビュータ (Red Hat なら Red Hat 社、Fedora Core なら Fedora Project など) が製作したものでなければならない。もっと厳密なことを言えば、複数のバージョンを同時にサポートしている場合、バージョンをまたいで同時にパッチを配布する再には、間違ったバージョンでパッチがインストールされてしまう (事によって動作がおかしくなったり動かなくなっちゃったりする) ことを防ぐという意味でも、この「正しいパッチであることを確認する」ということが重要になってくるわけだ。
DRM 技術はこの「正しいパッチであることを確認する」為の機構としても有効に活用ができる、優れたツールでもあるってこと。逆にいえば、この技術が正しく運用できないようでは、入手したパッチが正しいパッチであるかどうかを確実に確認する手段が失われてしまうということでもある。ディストリビュータが運営しているサイトからダウンロードしたつもりでも、もしかしたらフィッシングサイトに騙されて偽者をつかまされているかもしれない。自動更新ツールそのものに欠陥があれば、ワームによって挙動を捻じ曲げられ、偽者をダウンロードさせられてしまうかもしれない。そういった脅威から、確実に正しいパッチだけがインストールされるようにするための最後の砦、それこそが、パッチそのものの暗号化技術、すなわち DRM 技術である、というわけだ。
まぁ、DRM って言葉自体がそもそも「著作権保護」という意味を含んじゃっているので、こういった用途で使用する場合の同技術を DRM 技術と呼んでしまうことにはいささか抵抗を感じるわけだけれども、重要なのは、ライセンスはツールが提供する方法論までもを制限するべきではないってことなんだろうね。少なくとも、リーナス氏の主張は実に正当なものである、とおいらは思うよ。
永田寿康を笑え。そして民主党を笑え。 ― 2006年02月23日 15時20分55秒
はいはいサヨナラスサヨナラス
で、櫻井よしこたん。
また、ジャーナリストの櫻井よしこさんは、「永田議員のやる気は分かるが、民主党はこのメールのあやふやさを分かっていたはず。それでも強気に徹した前原代表の政治手法は未熟と言わざるを得ない。ただ、この問題は、武部幹事長らが堀江被告を選挙で公認並みの応援をしたことへの批判でもあった。一連の騒動で、民主が間違いで自民が正しいという風潮になることは避けるべきだ」と語った。
そういう風潮になるのを避けるように尽力せなあかんのは他でもない民主党自身であることは紛れもなく真実であるかと思われますがどうなんでしょかね。;-)


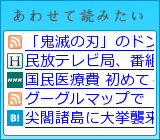





最近のコメント