毎日 Wikipedia 誤報の問題点 ― 2008年11月20日 11時44分16秒
毎日新聞が元更生事務次官らの連続殺傷事件に絡み、Wikipedia ユーザーのログイン名を晒して犯行予告者扱いした誤報について、Web上では既に毎日新聞の問題点がいくつか指摘されている。
- おわび:「ネットに犯行示唆?」の記事について - 毎日jp(毎日新聞)
- 【元厚生次官ら連続殺傷】毎日報道「ネットに犯行示唆」は誤報 (1/2ページ) - MSN産経ニュース
- ログインネームは匿名でも偽名でもないことを知るべきだ - 狐の王国
- 毎日新聞の誤報、ミスよりも深刻な社会部的な取材手法 - ガ島通信
id:KoshianX さめの主張も藤代さめの主張もごもっともなんだけれども、個人的にこれは問題なんじゃないかと思う点について軽く列挙してみようと思う。
容疑者にもなっていない人を犯罪者扱いする報道は許されるべきか?
id:KoshianX さめの主張とも若干かぶるんだけれども、個人を特定する情報を晒してしまうということ以前に、ジャーナリズムが犯人探しに加担するのは職責から外れるのではないか、とかちょっと思った。ただ、ジャーナリズムは事実・真実の探求を代行するお仕事である以上、それに準ずるような行動も時として必要なのかもしれない。例えばけーさつが重要な事実を隠しているようなケースであれば、それを暴き、衆目に晒すようなジャーナリズムは賞揚されるべきだ。
いずれにせよ、慎重に精査する必要はあると思う。今回の件では、結果として、この精査が足りなかった。もちろん、当該誤報が掲載された朝刊を引用して報じてしまったテレビ番組も然りで、新聞を信用しきって鵜呑みにするのではなく、各番組の責任において十分な裏取りを行うべきだ。
表層だけ見て記事にするのではなく、もっと深いところまで調べるべきだ。
失敗は誰にでもある。新聞記者だって間違える時は間違えるんである。そこは、読み手が理解した上で、情報との距離の取り方を学んで行くべきだと思う。
一方、失敗は学習の宝庫でもある。失敗した人間は考え、学び、その教訓を次に生かすべきだ。我々はそうした営みを「反省」と呼ぶ。
では、今回の失敗を犯してしまった記者は、何をどう、反省すべきか? ここで、Wikipedia が時刻を UTC で表示する事にばかり着目し、「ネットや IT を知らないからいけないんだ。もっとこれらを学ぼう」とか言ってそれっぽい How To 本を買いに走るのは、まったくの無駄だとは言わないが、ジャーナリストとしてはイマイチだと思う。たとえ、日本の Wikipedia の時刻表示がグリニッジ天文台基準であった事を知らなかったとしても、今回疑われた Wikipedia 編集人の Popons さんについて、より深く追求して調べていれば、犯す可能性の低い間違いだったのではないか。例えば、Popons さんの過去の投稿記録を追って調べれば、彼がどれだけ Wikipedia に貢献してきた人か、あるいは彼がどういったことに興味・感心を持っているか、といったこと、すなわち人物像が浮かび上がってくる。そして、そのような人が、愛しているはずの Wikipedia という場を、犯行予告などという行為で汚すという行動の不自然さを思えば、これをネタとして出稿することにもう少し慎重になれたはずだ。
署名がないので文責が不在。
責任という観点においては藤代さめの主張とも被るが、誤報の記事にもお詫びの記事にも署名がなく、毎日新聞社のどの記者に文責があるのかが不明である。これは今回の件に限らず他の多くの記事においても、あるいは他の新聞社においても同様であるが、記事の責任を会社が担保するというやり方が、個々の記者の責任感を薄めてしまっている可能性はもう少し考慮されるべきと思う。特に、ガバナンスがなく個々の社員が自由奔放であることが売りの毎日新聞社であればこそ、個別の記者の顔が読者にもっとよく見えてもいいはずだ。せっかく、人気の名物記者が生まれる素地が社内文化として確立しているのに、それを積極的に売り込まないのはもったいないとさえ思う。
スタンドプレーが過ぎる可能性; 社内コミュニケーションは大丈夫か?
で、スタンドプレーと言えば聞こえはいいが、要するに個々の社員が孤立していて、記者同士でのコミュニケーションが希薄だったりするような空気が蔓延しているんじゃないか、とも危惧した。まぁ、他にも何人かが当該記事に目を通していて、誰もがこりゃあ凄い、よく見つけたねと褒めまくっていた可能性も十分にあるので何とも言えないんだが、例えば取材チームみたいなのを組んでいて、チーム内でネタのレビューをすることによって、ネタのプロットに対する疑問点が洗い出され、ニュースとしての精度が上がっていく、といったような段取りは無いのか? 上司であるところのデスクの承認、だけでは、やっぱり情報の精度を維持するのにも限界があると思う。情報にスピードが求められるならばこれはなおさらで、短時間で精度を上げるなら、やっぱりある程度の人数をかけるしかないんじゃないかと思う。
とりあえずこんなところで…。
裁判と報道、それから司法のこれからについて。 ― 2007年09月22日 03時30分19秒
すまん、おいらの意見は概ね正反対。
偏向報道について。
ブログの流行により、報道に対して関係者がネット上で真意を明かしたり、実際の言論の詳細について追加検証を行ったりといった記事が時折見られるようになった。しかし、全般としては、現行の新聞・TV 報道を見た感想を述べるにとどまるブログがほとんどであるように思う。
はてなブックマークのようなソーシャルブックマークがもっと普及していけば、そういった報道への感想の言及はそっちに流れていくことになるかもしれない。mixi のような馴れ合いメディアとしての SNS や、Twitter のような、ブログよりも軽いメディアが使われるようになっていくことで、そうした流れはますます加速するのかもしれない。
もっとも、当の新聞・TV といった報道系メディアは、まだまだブログ上で見られる言説のほとんどがジャーナリズム性の薄いもので、ニュースの情報を握っていてジャーナリズムを発揮するイニシアチブは自分たちにあるという自負を持っているように思う。実際、政治の場における記者クラブによる締め出しなど、国民にとって重要な情報の取り扱いは主要新聞・TV局各社に牛耳られており、手出しできない状況は崩されていない (もっともそんなマスコミの偏向報道を嫌がって記者会見の全文を公表しちゃう小泉首相官邸サイトなんて例もあったりしますが)。
裁判の傍聴録なんかもその急先鋒で、マスコミは自分たちの押す論調を曲げずに済ませるための最も都合の良いトリミングを図って、記事として纏め上げたりするわけです。
この辺の記事も、参考までに、ぜひ、読んでみて頂きたいと思う。後者の例の発言については、確かに被害者感情を逆なでするものであり、不適切であるとは思うけれども、前後の文脈を切り捨てて報道するマスコミのやり方もまた、適切であるとは到底思えません。
マスコミは率を取るために、多くの国民の感情に沿う方向で物語を組み立て、報道記事をでっち上げています。もっと言えば、どういうシナリオを描けば国民感情をより効果的に煽れるのか、といったことを熟知しています。一方で、この事件ではありませんが、秋田県藤里町の連続児童殺人事件について、秋田県は県内に東京から派遣されている弁護士一人しかいないいわゆる弁護士過疎地であり (Sun Sep 23 20:00:54 JST 2007 - 訂正: コメントにて小倉氏より指摘がありました。県下で一人というのは事実ではないようです。詳細は記事文末を参照)、しかも裁判前の準備調査の結果が、後から派遣された別の弁護士に引き継がれていることを指摘した NHK の報道に、これ、ジャーナリズムとしてあるべき当然の指摘であるにもかかわらず、とんでもない良心を感じてしまうのであります。
弁護士は増やすべきか?
結論から言えば増やすべきです。日影なすやんはこれ以上質の悪い弁護士を増やすべきではないとしていますが、実際弁護士の質が悪いのは、法について責任を持って語れる人材が極端に少ないからという事情もあるのではないかと思っています。少なくとも、先に挙げた秋田の例のように、県内に自分ひとりっきりしか弁護士がいないという状況下で何年も働いていれば、知識も思想も仕事に対する姿勢でさえも偏向してしまうのは致し方ないのではないかと思います。そういう意味では、メディアに出て積極的に発言している橋下弁護士の姿勢には敬服します。発言内容は微妙にあれですが。
要は橋下弁護士がアフォだと思うならば同じくメディアに出て看破してやればよいのです。そういう弁護士がもっと出てきたっていい。法に関する話題が盛んに取り交わされるにつれ、国民の法に関する関心も高まるでしょう。そうした下地は、今後陪審員制度を運用する上でも非常に大切なことであるはずです。
立法に携わる国会議員の中に、司法経験者が少ないというのも問題です。立法のための人材を育成するという意味でも、司法資格の門戸を広げることは重要です。
もっとも、司法試験を簡単にすればいい、という考え方には、安直さを感じます。そういう問題ではないだろうと思います。実際、現行の難しい司法試験を通過して、アフォなことをやっている弁護士というのは多くいるのですから、そこが必ずしも重要ではないというのは明らかなはずです。
個人的には、短答式・論文式含めて、ペーパーテスト一発で合否を判定するというやり方自体に無理があると思っています。問題の質を変えずに合格基準を下げ、それを通過した人間に対して、3年以上の現場における補助実務を義務付け、その間に挙げた功績等により資格の交付を判定する、といったような、もっと現実的な方法に切り替えるべきなのではないでしょうか?
コメント欄にて小倉秀夫さんよりご指摘いただいたように、「秋田県内で弁護士が一人しかいない」という記述は誤りでした。NHK のニュースについてはうろ覚えであったため、情報が正確ではありませんでした。大変失礼いたしました。
名簿の中に「藤里町」が無いので、「秋田県内で一人」ではなく、「藤里町内で一人」と言っていたのかもしれません (そもそも、「一人」という人数も、もしかしたら記憶違いだったかもしれません)。
読み逃げ ― 2007年03月21日 00時20分13秒
- 「mixi読み逃げ」ってダメなの? (ITmedia)
一応断っておこう。おいらは「まだ」mixi 会員になっていない。だから mixi のシステムに関する誤解があるかもしれない。その点についてはご指摘いただければと思う。
キモになるのは「マイミク」という機能なんではないかと思う。
「マイミクの1人に、自分の日記を読み逃げされている。いったい何を考えているのか」――先週末、ユーザーが質問・回答するサイト「OKWave」に投稿されたこんな質問が、ネット上で話題になった。回答には「確かに失礼で常識がない人ですね」「そんな人はアクセス禁止にしてしまいしょう」など、「読み逃げは非常識・失礼」とする立場からの意見が多く寄せられた。
この質問記事におけるやり取りにおいては、「読み逃げ」に対する強い違和感の表明といえそうなのは Lupinus という方一人だけ。全体を通してみると、mixi 内の文脈においては「まともな感覚」であると言えるのではないかと思う。
そのことは、質問内容の以下の部分からも読み取れる。
それなのにそのマイミクは、
'日記にコメントが少なくて寂しい~。素通りは悲しいからやめてね♪’と自分の日記には書いています。
そしてほぼ毎日自分の日記を書いています。
彼女は自分が読み逃げをしているという意識はゼロかと思いますが、どんな考え方なんでしょうか?
自分にしか興味がないのか、自分の伝説をよく書いています。
ミクシィで悩みたくはないし、このマイミクのように他人に興味がない人とは、
お付き合いできそうにないと思っています。
ちなみに Lupinus 氏の疑問に対する回答は、不十分というか言葉足らずなんではないかと思う。
マイミクシィという機能について誤解があったら失礼なのですが、こいつは確か、こんな機能だったような気がするのですが。。。
- 友達認定したユーザーをリストアップする機能。
- マイミクに登録したユーザーだけが閲覧可能な日記を書くことが可能。
どこかから聞いた話によると、
- 見知らぬ人から「お友達になって欲しい」(=マイミクに登録して欲しい) と言い寄られ、(そういうもんなんだと思って) ついついマイミクに登録してしまう。
- 1 で登録した人がマイミク向け日記を読むだけ読んで何にも反応してこない。
- 1 で登録した人の狙いがよく分からない。キモチワルイ。
。。。みたいなことが結構あるんだそうで、なるほど、そりゃあ確かに気持ち悪いと思われてしまっても仕方ないかなと思う。
でもそれって、本質的には「読み逃げだから」気持ち悪いわけではなくて、理由はもうちょっと別のところにあるはずなんだけれども、「読み逃げ」っていう部分だけがマナー違反として切り取られて一人歩きしてしまって、現在に至る。って言う感じなんじゃないかとおいら的には思うわけだ。
そうなんだとしたら OKWave で質問のやり取りをしていた人たちはまだ「まとも」だと思う。彼らは mixi という道具を利用して、新たなコミュニケーションの輪を広げようと努力していた人々だ。そして彼らなりに考えて得た処世術が、その場で披露されているわけだ。逆に mixi 日記やプロフィールにとりあえず「読み逃げ禁止」とか書いちゃっている人は、何故それを禁止しなければならないのかについて一考を案じているのかどうかで、まともなのか思考停止なのかは分かれるところだと思う。
一方で、通常の Web サイトやブログなどしか基準にみれずにはてぶや 2ちゃんねるで不快感を表明しているだけの連中はそれこそほぼ確実に思考停止なんじゃないかと思う。そういう状況に至ってしまうまでの「何故」を考察できないようでは、この一件から得られるものは何も無いんじゃないか? そういう意味では件の記事は単なる煽り記事でしかなく、価値は薄いと言わざるを得ない。
元来、mixi が持て囃された一番の理由は、招待制とし、実名を公開しあうことによって、旧友との再開の場を得られる点にあったのではないかと思う。だからこそ、マイミクのような機能がありがたがられたのではないか? それは本来、新たに友達になれるかもしれない人を登録するためのものではなく、既に知り合っている、気を許している仲である人をピックアップする為のものなのではないかと思う。だからこそ、そういう仲の人になら見せられる日記も書きたい、というニーズが生きてくるわけだし、交流を再び深める為の場としてうまく機能してきたのではないのか?
「読み逃げ禁止」騒動を通して、mixi 運営の本来の原点から、随分と路線がずれてきてしまっているかもしれない実態について、いろいろと透けて見えてくるものがあるのではないかと思う。その視点は、mixi 株主にとってはあんまり利益にならないかもしれないが、mixi 運営に携わる人間や mixi をまともに利用するユーザー達にとっては、それなりに利益になる話になるのではないかと思う。
単に「読み逃げ禁止」としてしまう前に、もう一度、マイミクの利用のあり方、更にはネットを介したコミュニケーションのあり方について、ご一考案じてみてはいかがかと思う。
なんか OKWave の質問記事が削除されてるんだが (-_-; 。かなり信憑性の高い「ネタだ」っつー意見もちらほら。
。。。やっぱり一次情報はちゃんと隅々まで見ないとダメだなー。
まぁでも「読み逃げ禁止」って記述自体は実際あるみたいだし、そういう意味では一応問題提起ぐらいにはなってるようだから、まったく無意味な議論とも思わないけどね。
プライバシー権とは、自分をどういう人間であるように見せたいのかをコントロールする権利である。 ― 2007年02月17日 09時39分18秒
この報道自体は、現行法においてはプライバシー権の侵害には当たらないかもしれない。が、もはやツールを用いて同定可能なプライバシー情報の一部を市民の耳目に晒す行為が、如何に腐敗したジャーナリズムであるかを記者はもっと認識し、深く反省すべきだ。
柳沢厚労大臣2/6発言がどう問題なのかが理解できない件 ― 2007年02月07日 08時56分16秒
- 柳沢厚労相が辞任トドメの失言 (スポーツニッポン)
- 「結婚・子2人は健全」 厚労相発言、与党内からも批判 (朝日新聞)
若者の結婚、出産への意識が多様化する中、柳沢氏の配慮を欠いた発言が飛び出したのは6日の閣議後の記者会見。今後の少子化対策について「若い人たちは結婚したい、子供を2人以上持ちたいという(希望を持つ)きわめて健全な状況にいる」と話した。
厚労省が行った意識調査で、未婚男女の約8割超が「子供を2人以上欲しい」との回答をふまえての“持論”だったが、子供が2人以上いないと不健全であるという印象を与えかねない表現だとして、男女議員が反発。身内であるはずの与党からも「2度目の不適切発言」「こう問題が続くと守りきれない」など批判の声がもれた。
(中略)
野党側も一斉に反発。社民党の福島みずほ党首は「本人の考え方が全然ダメ。考え方の根底には女性不在、当事者不在で頭数で2人がいいと思い込んでいる」と怒り心頭。民主党の太田和美衆院議員は「(未婚の)私は不健全になる訳ですね」とあきれた顔。ある野党参院議員は、柳沢氏に2人の子供がいることに触れ「柳沢家は健全で、(子供がいない)安倍首相の家は健全じゃないという意味にも取れる」とチクリ。野党側は柳沢氏辞任だけでなく、安倍首相の任命責任を追及していく構えだ。
発言内容の解釈を、「論理的思考を持とうとしない人間の脊椎反射的表出」を基準に捉えるのはどうかと思う。「子どもを二人以上持ちたがっている人は健全」というのは確かに短絡的かもしれない。もっとも、政府が行う意識調査に対して、不健全な欲求を前提に「子作りに励みま~っす♥」とか答える馬鹿は少ない気もするけどな。でも「子どもを持ちたい」と願う人の思いを「健全である」と評価すること自体に何らかの問題があるとは到底思えない。この科白を問題視する人こそ、不健全な偏見を根底に抱いているんじゃないのか?
そして、「子どもを二人以上持ちたがっている人は健全」→「子どもを二人以上持たない人は不健全」という解釈に直結する意味が分からない。「子どもを持ちたいと願う人」を「健全である」と評価する考えと、「子どもを持ちたいとは願わない人」を「健全ではない」と評価する考えは、必ずしも直結するものでは無いんじゃないのか?
「子どもを持ちたい」とする人の思い、あるいは、「子どもを持とうとする」が故に行う男女の営みは、紛れもなく「健全な思い」「健全な営み」の一つであると言い切れるのか。否、「子どもを持ちたい」と思うに至る動機次第では必ずしも健全とは言い切れないかもしれない (そしてそういう意味でのみ、この考えを「短絡的だ」と断ずることは可能だ)。しかし、それと同様に、「子どもを持ちたい」とは思わない (もしくは「あまり」思わない) 人が、それ以外の関心事に対して、思い、あるいはそれを遂げようとするがゆえに行う営みに対しても、「健全である」と評価できる場合もあるしできない場合もあるだろう。
そうした様々な関心事に対する思いや営みの一つ一つに対して、「健全である」とする評価を「一般的に決め付けること」は確かに短絡的かもしれないが、しかし個々人の数ある思いや営みが相対的に、より強く、より活動的であるならば、それらの一つ一つの思いや営みは「より健全である」と評価することに違和感は無いし、同意できる。そうした思い、営みの一つに「出産および子育て」があることは紛れも無い真実だ。
つまり、「(二人以上) 子どもを持ちたい」という思いを「健全」と評するのは、「(女性であっても) 社会に出て働きたい」という思いを「健全」と評するのと、価値感的にはそれほど大差ない筈だ。どちらも、個々人が背景に持ちうる動機を考慮しないという意味では同じように「短絡的」ではあるが、それらの思いや営みの総体が個々人および社会に利する効果を基準として評価するならば、そういう思いが募るならば募るほど、あるいはそういう営みがより活動的であるほど、「より健全である」と評することはそれなりに妥当であると思う。
どう考えても、柳沢氏の「若い人たちは結婚したい、子供を2人以上持ちたいというきわめて健全な状況にいる」
とする発言に、非ジェンダーフリー的・性差別的な価値観を汲み取ることは、おいらにはできない。周辺議員 (特に野党) やマスコミはヒステリックに過ぎるんじゃないか?
柳沢氏は6日夜、記者団に「若い人たちの意識を説明した。文脈をよくみていただければ、誤解されることはない」と述べ、発言を撤回しなかった。結婚しない、または子どもを欲しがらない人たちが「不健全」と解釈される可能性については「子どもを産む産まない、結婚するしない、こういうものは個々人の自由意思で決まるという前提のもとで社会が成り立っている」と述べ、女性に出産を強要する考えはないことを強調した。
文脈については、会見内容が厚労省のサイトにそのうち掲載されるはずである。内容次第ではまた何か書くかも。
ギザヘナード事件 ― 2007年02月01日 15時18分35秒
しかし大変な事件がおきましたね。ネット上にはまだニュース記事が出てきていないようなので、新聞記事から以下、抜粋しておきますね。
鼻歌を歌いながら著作権使用料の支払いを拒否するのは違法として、日本音楽著作権協会が館山市のレストラン「ギザヘナード」経営者の鼻之下伸夫さん(56)を相手に鼻歌差し止めなどを求めた訴訟の判決が30日、千葉地裁であった。山田淳次裁判長は「将来的にも著作権侵害行為を続ける恐れがある」として演奏差し止めや鼻毛の除去、損害金約 190万円の支払いなどを命じる判決を言い渡した。
しかし今後はアレだね、むかつくお店を潰すには、そのお店に毎日通って歌を歌えばいいんだ。実に簡単だね。。。!!
ジャーナリストは、決して誇れる仕事じゃない。 ― 2007年01月31日 13時16分54秒
内田センセーのブログ記事に書かれたこのコメントにえらく感心しますた。そんだけ。
視聴者側のメディアリテラシーの「底上げ」は必要だと思うよ。 ― 2007年01月31日 09時35分08秒
- テレビに「期待」してはいけない (池田信夫 blog さま)
- リテラシーに「期待」してはいけない (404 Blog Not Found さま)
- 目標はリテラシーの高度化ではない (worldNote さま)
先日の「あるある」も今回のNHKの事件もそうだが、視聴者や取材相手にリテラシーがなく、テレビを信用しすぎていることが間違いのもとだ。誤解を恐れずにいえば、あるあるの実験なんて毎回ブログなどで笑いものになっていたネタである。健康にきくすごい食品が、毎週みつかって500回以上も続くわけがない。作る側も、被験者を「出演者」だと思って演技をつけていたのではないか(それがいいと言っているわけではありませんよ、念のため)。
テレビは(報道も含めて)本質的には娯楽であり、そこに出す情報を選ぶ基準は、おもしろいかどうかだ。NHKでも、番組の最大のほめ言葉は「おもしろかったね」であって、「勉強になったよ」というのは半分皮肉である。NHKを叩いた朝日新聞だって、「政治家が介入した」というストーリーにしたほうがおもしろいから、そういう話を捏造したのだろう。
なぜTVの品質が他のメディアより厳しく問われるべきかといえば、それが最も理解しやすく、最も視聴され、それゆえ最も期待されているメディアだから。相対的に地位が下がっているというのは、品質低下の言い訳にならない。日本人がコメをあまり食べなくなったからといって、コメに麻薬や覚醒剤を入れていいということにはならない。メディアの側(池田氏がそうだというつもりはない)が視聴者のリテラシーにケチをつけるのは、牛乳を飲んでいたと思ったらそれが牛乳味のウンコで(食事中の方失礼!)、それを咎めたら「お前の舌がバカだ」というのに等しい無礼ではないか。
私個人は、TVを巡る諸法規は食品衛生法と同程度に厳しくてしかるべきだと考えている。「文句があるなら消せばいい」というのは「文句があるなら食わなきゃいい」というのと同義だ。無料だというのはいいわけにならない。なるなら公園の水道水を子供が飲んで腹を壊したとしても、管理する自治体は免責されなければならない。
世論を作り出す機能は、政府だけでなく、大衆商品を販売する企業にも、有利な世論、商品の購買やブランドイメージを高める装置として活用された。必要とされるのは、リテラシーの高度化ではなく、影響される(操作可能な)大衆だ。もちろん、政府としては、あまりに流れすぎても困るから、何が「正しい」とか、何が「道徳的」であるとかにも、こだわりを残す。つまり、リテラシーがあまりにも無い状態も困る。中間に、リテラシーのちょうど良い加減があるのだ。あまりにもリテラシーが高すぎたら、「占い」コーナーは絶滅するし、根拠のない「不安」が減れば、不安をネタにする商売の大半が立ち行かなくなる。そんな事では、景気を悪くしかねない。
先日紹介した番組を見ていても思ったのですが、現実問題として TV 視聴者であるところの大衆のメディアリテラシーが平均的に決して高くはなくて、その現実に報道関係者が寄りかかっちゃっている部分はあるんじゃないかな、とは思うわけですよ。だからこの問題は、報道関係者の襟を正すだけで解決できることではなくて、視聴者すなわち大衆のメディアリテラシーが底上げされ、大衆から声が上がるような状況も醸成されないといけないんだろうな、とは思う。
重要なのはそのための仕組みで、結局のところ教育の問題になってくるわけだけれども、一方でその教育を学校すなわち教育行政に任せてしまっていたのでは、それが国、すなわち中央から下りてくるものとして機能している限りは期待できないでしょう。その辺の思惑については worldNote の中の人が指摘してくださっているし、なにより記者クラブという仕組みがそのことをまさに象徴しているわけで。
教育行政の地方自治の重要性については週間ミヤダイの「2006年12月08日更新分」でも語られているけれども、国による思惑からの独立、という意味でも重要になってくるんじゃないかと思う。
dankogai さんは iliterate な人でも理解できるメディアとして、TV は視聴者のリテラシーを高める役割も担わなきゃあかんと主張されている。おいらはそういう TV 報道が「あってもいいな」とは思うし、そういう番組があったら是非見てみたいとも思う。ただ、その義務を負う責としては、むしろ義務教育の方にあるんじゃないかと思う。憲法は親が子どもを文盲に育ててはいけないことを義務として定めている。でも、ここで言うところの literacy ってのは、文字が読めて文章が読めて、っていうこと以上のこと、どちらかというと「文脈を読んで理解できる能力」のことを指すんじゃないかと思う。これは確かに高度な技能で、そうそう簡単に誰にでも備わる能力じゃないし、歳をとったりコミュニケーションをある程度疎かにしてみたりするだけで割と簡単に衰えたりもする能力だ。だからこそ、それが弱いことが悪いと一方的に視聴者に責任を負わせるような姿勢はアンフェアだとは思うけれども、だからといってじゃあその能力の醸成を TV が担わなきゃあかんのかというとそれもまた筋違いだと思う。
少なくとも、構図として、いくつかの TV 番組、いや、あるいはほぼ全てと言えてしまうかも知れないけれども、つまりは TV が視聴者を騙す、という構図になっている。その構図が存在する元で、TV に視聴者のメディアリテラシーの底上げを行うような番組が作られたとして、いったいどれだけの人がその番組の内容を視聴し、信用するだろう? 結局、メディアリテラシーが低い多くの人々は、興味がないから視聴しないか、その番組を信用しつつ視聴するかのどちらかだろう。じゃあ、その番組内で語られる「メディアリテラシー」とやらが、実際のところ本当に正当なものであることが果たしてどれほど期待できるのか?
どっちにせよ、TV にせよ何にせよその手の報道メディア以外の第3勢力が、高いリテラシーに基づいて報道を監視するような構図が必要になるんじゃないかとおいらは思う。今のところそういう意味でもっとも有望視できるのは実はインターネット、Web 上でのやり取りなわけだけれど、これこそまさに純然たる「大衆による自衛」の構図だ。本来その担い手は「教育」にあるべきなのではないのか? そして大衆による自衛は、あくまで教育を補完する為のものとして機能すべきものなのではないのか?
おいらが視聴者側におけるメディアリテラシーの底上げも必要だと思うのは、まさにこうした「大衆による自衛」がより有効に機能するためである。一方で、それだけでは到底覆しえない利権構造的な問題も多々ある。記者クラブにおける「16社以外締め出し」の件然り、電波法による規制然り、トヨタや松下みたいなスポンサージャックの問題然り。もちろん報道する側のメディアリテラシーの底上げも重要でしょう。下請け構造の問題然り、報道番組的な内容をバラエティ番組として扱うことの問題然り、CM 出演するみのもんたの件然り。
どちらか一方だけを引き締めればいいという問題じゃあない。大衆いじめ的な視聴者への責任押し付け論がまかり通っていいとは思えないけれども、だからといって自衛を放棄する愚者の大衆に同情の余地があるとも到底思えないです。
「日本のTV報道がいかに腐っているか」 ― 2007年01月30日 22時43分28秒
YouTube にて、表題のフレーズで検索して出てくる番組が熱い。これ、続き観たいなぁ。。。
ちなみに「朝日ニュースター」をスカパーで契約したいんだけど、契約変更のページが重くて繋がらん。。。明日やるか。
「恣意的な波線」は、むしろアリだと思う ― 2007年01月30日 09時10分48秒
これが「無意識に」「非意図的に」使われちゃってるってのが、問題っちゅーか頭が悪いっちゅーか。
2つ例が紹介されていて、1つ目の例については賛成意見が多いものの、2つ目については賛否両論分かれている模様。
1つ目がまずいのは、波線すらないから。それどころか、目盛りに数字すら振られていない。各グラフに数字が振られているとはいえ、これは確かに大きな誤解を招くと思う。
しかし 2つ目の例については、波線は書かれているし、目盛りにも数字が振られている。見た目のデザイン的には、個人的には波線が入る部位をもう少し長めに余白を取って、さらに破線自体の白抜きの太さももっと太めに取る、つまり、目盛りが一部省略されていると言うことがもっとしっかり強調されている方がいいな、とは思うけど、このデザイン自体が決定的にまずいのかといわれると、うーん、と頭を捻ってしまうのは、単においらがこの手のグラフの描かれ方を見慣れてしまったから、つまり、慣例として心理的に受け入れちゃっているからだからなんだろうか、とは思わなくも無く。
ただ、心配なのは、こうしたグラフにおける「波線」の使用が、変化を強調したい為に用いられる演出であることを理解せずに使用しているケースが少なくない、ということ。高木さんは記事中で以下のようにおっさられているわけですが (強調は T.MURACHI による)、
これも悪意を持って印象操作したわけではないのだろう。テレビではいちいち増えたとか減ったとか言わないと気が済まないのではないか? データをグラフで示すというのは、なにも変化があることを示すためだけじゃない。「変化がない」ことを示すことも立派な重要な情報であるはずだ。「横ばい」と言えばいいものをわざわざ拡大して無理に「増加している」だの言う様子は、NHKでさえ見かける。
変化があることを示したかったにしても、サンプルが年単位でたったの 6年間でしかないというのはあんまりにも少なすぎるという意味で説得力は低いわけですが、そもそも元となる記事の内容を見ても、これが「全国における海難審判の件数はやや増加傾向にある」ということを伝えたいジャーナリズムであるようには、どこをどう縦読みしても見えない、という点にこそ、問題があるんじゃないかと思う。
つまり、「なんとなく見栄えのあるグラフにしたい」という潜在的な欲求が、あんまり意味のない波線の挿入へと駆り立て、その結果、本来伝えるようなことではないような事柄を、読者や視聴者に勝手に読み取られているということが、少なからず発生しているんではないかと思う。あるいは、そうした報道が、別の報道機関やミニコミや一部の詐欺師などに悪用されるケースも、無いとは言えないんじゃないかと勘ぐってしまう。
悪用例を、ここですぐさま示すことができればいいんだけど、今回思いつきでこの記事書いてるので\(^O^)/ (てゆか、それは「今回」じゃなくて「いつも」だろ>ヲレ\(^O^)/)、すぐには示せないのが残念ではあるのでございますが。。。
ただ、おいらとしては、グラフに波線を使用する、まぁ確かに、科学的なことを言えば、本来この手の波線は、すべてのサンプルに共通する部分を省略する為ではなくて、一部の特異なサンプルによる突出が紙面で表示しきれない場合の例外措置として使用されるべきなのは言うまでも無いのですが、そうではなくて、あくまで変化を強調したい、という目的があって波線を使用する、のであれば、そのような強調表現が行われているということを紙面で、あるいは TV 報道ならばキャスターが口答で、はっきりとその事実と意図を記述もしくは公言すべきではあると思う。そして、記述もしくは公言するほどの意図がないのであれば、そんな無意味な波線表記は避けるべきなんだろうな、と思う。
んー、こうしてまとめると、タイトルほど (グラフの波線に対して) 肯定的じゃないなw。こういうタイトルの付け方もやっぱり「恣意的」で「捏造」になっちゃうのかしら? \(^O^)/


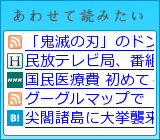





最近のコメント