社会問題としての「非モテ」考 ― 2008年08月02日 22時35分43秒
前回の記事は本当にどこにも tb 飛ばさなかったので、誰にも見かけられないままひっそりと沈んでいくんじゃないかと、別に不安になる必要のないことで不安になってしまい、気弱にもついったに URL を載せるなんて恥ずかしい真似をしていたりしたおいらだったわけでつがw、そんなおいらの思いとは裏腹に、過去最高のブクマ数を稼ぐという結果に、少々驚きを隠せません。あの件、みんなそんなに気に障っていたのか。(^_^;
んで、その中で一つ、おいらにとってとても耳の痛い指摘をしてくださった方がいらっさいました。
uumin3 「非モテ」だって社会問題として考えれば侮蔑しなくても…とちょっと思わないでもなかったり。⇒http://d.hatena.ne.jp/uumin3/20070516#p3 (非モテ論議と格差社会論議は意外に似ている)
これはまさしく先日のこちらのエントリの事を指しているのではないかと思う。一応、差別的な思考であった点については後日のエントリで言い訳させていただいた通りで、誠に反省至極なのであります。
今回のエントリはその、「非モテ」を自称されている方々にとっては、傷に塩を塗り込む物かも知れません。
「モテ」と「非モテ」、特殊なのはどちらか?
で、「非モテ」という言葉について再考してみたいのですが、これが差別的なレッテルとして用いられるに至る以前に、そもそも「モテない」という状態に陥っている人々を十把一絡げに括りたいという意志があったのかどうかという点が、何気に争点になるのではないかと思いました。というのも、これはおいら個人の価値観に過ぎないのかも知れないのですが、そもそも「モテない」という状態よりも、「モテる」という状態の方が、実は特別な状態であると言えるのではないかと思っているからです。
モテるってのは、よーするに「人気があって、ちやほやされる」状態のことを指すわけですが、異性に限らず特定の集団にモテている人がいる場合、その理由として、その人に特別な魅力が備わっているから、ということが言えるのではないでしょうか。dankogai や Matz が一部の (特に Web 系の) プログラマーにモテているのは、彼らがその道に携わる者として、特別な成果を上げ、特別な信念を持ち、それらが特別な魅力を発揮しているからでしょう。
その一方で、モテている人が観測されるときに、その人がモテている理由を理解できない人や、その人の発揮する魅力にそれほどの魅力というか価値を感じない人にとっては、逆に妬みの対象となることが多いのではないでしょうか。子ども社会など、民度が十分に高くない社会においては、ある集団にモテている人間が、そこに接する別の集団からは陰湿ないじめに遭っている、というのはよくあることであるように思います。
モテる人間に対する偏見や差別がそれほど問題視されない理由として、彼らをもてはやす集団の存在が彼の心の支えとなり、救いとなっているという現実、あるいは (実際には救われていないのだとして、それでも) そう見られてしまいがちな現実、というのがあるのかも知れません。元より大衆の嫉妬心が、それを問題視させまいとする空気を醸成している可能性も、少しは鑑みた方がいいのかも知れません。
「モテる」という状態は能動的か?
そんなわけで、実際には「モテない」というのは極めてありふれた状態であり、本来であればそこにレッテルを醸成する余地はないはずでした。多くの人々はモテないなりに個別に交流を見出し、そうした中で個別に深い絆を醸成しながら、社会との繋がりを確立していたわけです。
しかしその一方で、「モテる」という状態を目指すことを奨励する言説も、古くからありました。たとえばそれは、アパレルや化粧品などの方面から多く発信されていました。異性にモテるという承認欲求を促すことが、彼らの商売に繋がっていたからです。
こうしたビジネスは、情報発信の主導権がテレビと出版にあった時代においては効果を発揮しました。きらびやかな芸能界は劇場に足を運ばずとも、お茶の間で見せつけられる物となり、かっこよさへの羨望が、若い子たちの間で共通前提として普及していたからです。そうした前提があってこそ、時代のカリスマが、様々なファッションを作り出していきました。六本木黒服文化、イタカジ、渋谷系、ガングロ、ルーソー、それからえーっと、何だっけ…?
実際にはそういった流行に乗らずともモテちゃっていた人はそれなりにいたし、必死に流行を追ってもやっぱりモテない人はいっぱいいました。しかしその一方で、モテてなかった人が運良く何らかの関係性に恵まれることがあったときに、そうした光景を目にした人々によって、流行を追うことの重要性が信じられるようになっていった、という経緯はあったのかも知れません。
いずれにせよ、「モテる」というのは単なる状態であり、形容詞的に用いられるべき可能動詞です。本来モテようとしてモテることができる訳ではなく、そのための確立された方法論が存在するわけでもありません。実際にモテている人からしてみれば、自分の意志とは無関係に「モテちゃっている」訳で、それはそれで必要以上の関係性が構築されていってしまうことによるリスクの増大という、割と無視できない苦労と同居するものです。
交流のハードル
他者との関係性を構築「できない」人々の存在が問題視されるようになったのは、割と最近のことではないでしょうか。それまでは、そういう人々が存在するという現実について、あまり直視されなかったように思います (直視できない人、直視したがらない人は、今でも恐らくいっぱいいます)。関係性を構築できない要因は様々ですが、その機会が学校や職場に拘束されることで制限されている可能性や、心身障害、精神疾患などにより、能力的に、あるいは社会的に構築が困難になっている可能性、更には家庭内での虐待やネグレクト、学校や職場でのいじめに起因するケースなどが注目されています。
一方で、他者との関係性を構築することへの心理的なハードルが、かつてより上がっている可能性についても、議論する必要があるかも知れません。
例えば核家族化の浸透、それを追うように、共働きが浸透していったこと、それから、かつては「9時から 5時まで」だった労働時間の常識が、休憩時間をカウントしない「実働 8時間」とフレックスタイム制の普及により、都市部の中小企業を中心に「10時から 7時、さらに残業」という常識へとシフトしていったという背景もあり、保護者が忙しすぎて子どもやその教育に関心を持てないという状態が醸成されていってしまいました (モンスターペアレントが問題視されるようになった背景の本質も、ここにあると考えていますが、これについては別の機会で)。
この結果、親同士、家庭同士の交流の機会が、かつてより少なくなっていき、「幼なじみ」という状況が作られる可能性も、子ども同士では解決しきれない揉め事への関与の機会も、子どもたちを安全に遊ばせられる場所、環境の提供も、できなくなってきているのではないか、という点については、まだあまり表だって議論されていないように思います。
こうした地域交流の希薄化が、関係性を構築し、醸成する機会を減らしていった結果、クラスメートに声をかけたり、放課後のお誘いをしたり、気に入らないことを注意したり、各自の趣味を明かしあったりといった行動に、余計な勇気を要するようになっていったのかも知れません。
そんな中、変わらないのは学校というシステムで、クラスという単位に箱詰めされ、班という単位に機械的に振り分けられ、担任教師にはクラス運営の効率化のために「仲良くしなさい」と教えられる。そして、どうしても誰とも仲良くできない子が、他者の互いに仲良くするという目的のためにいじめの対象として利用され、勇気のない多くの子たちがそんな状況を傍観する。
まぁそういう典型的ないじめの構図ってのは割と昔からあったのですが、最近ではケータイの普及などによる別レイヤーでの関係性が交流を複雑化し、共通前提を喪失させるために、場の空気が流動的になっている、とする見方もあるようですね。学校では仲良くしているし、放課後もつるんでいるときは普通に仲良くしているのに、「学校裏サイト」(と呼ばれる単なる Web 掲示板) ではあることないこと触れ回る奴が場を荒らして不安を煽り、疑心暗鬼を募らせるという…。まぁそこまで露骨なケースじゃなくても、顔を見せ合って会話しているときと文字で交流するときとでは心理的障壁の度合いというのは結構違うようで、ネットではなぜかギスギスした論争になってしまうというのは割とよく見かける光景なんじゃないでしょうか (あー草の根 BBS 時代が懐かしい…泣)。
友だちを「作りたい」という欲求が誤用として浮上するのはこの辺に端を発していて、要するに経験的に関係性を築くのは難しいことだという認識を育んでしまっている人というのが、おいらたち前後の世代以降では割と増えてきていることの証なんじゃないかと思います。これは先ほどの「能動的か否か」という話に繋がる要素で、実際には友だちってのも「作る」ものではなくて「できちゃう」ものだ、っていうのが現実です。人ってのは不思議な物で、自分には現状不可能なことほど、「何らかの努力によって可能にできる」ものだと思ってしまうもののようです。あるいはそう思いたいのでしょう。
「非モテ」を自称することの有用性
で、やっと「非モテ」の話になっていくわけですが、おいらの見立てではこの言葉はあくまで「モテない」という状態を指す場合にのみ用いるべき言葉であり、「非モテ」というレッテルを貼るべき集合が存在するわけではないのではないかと考えています。その一方で、自ら「非モテ」を称する人は、少なくともネット上ではそれなりにいらっさるようで、そうした人々の中には、「オタク」や「ヤンキー」、「スイーツ(笑)」などといったレッテルと同列の言葉として、「非モテ」を用いているきらいがあるように思います。
もちろん、「非モテ」がレッテルとして用いられるようになったことと、それを自称する人が出現したことに、直接の相関性はないでしょう。鶏が先か卵が先かを議論することに、あまり意味はありません。しかし、彼らが「非モテ」を自称することに、何らかのメリットを見出している可能性については、検討の余地があるかも知れません。
おいらはそれは、実は承認欲求に基づくものなのではないかと睨んでいます。すなわち、お互いに「非モテ」を自称しあうことによって、彼らの間に共通前提を作り出し、そこに関係性の土台を構築したいという意図です。これは、本来侮蔑の対象として作られたレッテルであるはずの言葉「オタク」を敢えて自称しあうことで、特定のカルチャーについて語り合う、より潤滑な土壌を作ろうとする人々の精神性に共通します。
彼らは「モテ」と「スイーツ(笑)」(ここでは「おれたちのカルチャーを理解できない糞女ども」ぐらいの意味) を共通の敵と認識し、敵と見なされる言質に対して苛ついてみせたり、敵意をむき出しにして見せたり、あきれかえって見せたり、反論して優越感ゲームに耽って見せたりします。そうすることで、お互いに共有するはずの精神性を確認し合い、馴れ合い、安心するのです。
もちろん、そういった馴れ合いごっこに荷担しないにも関わらず、「非モテ」を自称されるかたもいらっしゃいます。しかし、そういう方々が「非モテ」を自称する人々の文脈というか空気を読まない発言を試みると、やはり幾人かの自称「非モテ」たちの攻撃の対象となったりします。特に、「非モテだけど一応彼女が居ます」などとネット上で書こうものなら、たちまちの内に燃料となり、非モテ非承認の村八分騒ぎとなるのです。
もちろん、ふとしたきっかけで関係性に恵まれたために「非モテ」を卒業される人というのも一定数居続けるでしょうが、いずれにせよこうしたサイクルは「非モテ」を自称される方々に馴れ合いごっこ的な精神性が介在しているケースの純度を一定以上に保ち続けることとなるのではないでしょうか。
「非モテ」のレッテル化
こうした経緯が、「非モテ」という言葉のレッテルとしての価値性を高めるサイクルになっている可能性については、検討の余地があるかも知れません。というのも、後々になって初めて「非モテ」という用語に触れることになる新参者たちは、かなり純度の高い「非モテ」の精神性を、肌で感じてしまうことになるからです。非モテはキモイ。非モテは恐い。非モテはプライドも向上心もない。
そして、そうした差別的なレッテルによる幻想に対し、それを反面教師として捉えるのです。自分はこうならないよう気をつけよう。非モテにならないように気をつけよう。モテる人であろうとしよう!!
…本来、モテないという状態自体は、これっぽっちも、侮蔑の対象などには、なり得ませんでした。なりようが、ありませんでした。
モテない理由など、無限に存在するのです。むしろ、モテる理由の方が、非常に限られているのです。しかし、「非モテ」たちを見た人々は、彼らのそうした精神性に、モテない理由を見出そうとするでしょう。そして、自分だって大してモテる訳でもないのに、「非モテ」を差別の対象として見なすのです。
とりあえず「非モテ」を自称するのはもうやめないか?
以下はおいら個人の価値観です。こうした状況は、おいらは非常に不毛だと思っています。
もう、非モテを自称するのは、やめにしませんか?
実際のところ、モテないこと自体は、社会問題でも何でもないんです。個人の責任ですらありません。そもそもモテることは義務ではありません。
でも「非モテ」差別は社会問題です。なぜならこの状態は、そこに触れる人々に、「モテなきゃいけない」という固定的な価値観と、「モテても容易に知られてはいけない」という誤った倫理観を、脅迫的に押しつけてしまう可能性があるからです。これは、現状流布しているレッテルとしての「非モテ」の精神性に共感できないにも関わらず、現実問題としてモテていない人々にとっては、社会不安以外の何物でもありません。
そして、モテない人々が、そうした不安から逃れるには、2通りの方法しかありません。一つは、開き直って堂々とすること。もう一つは、自称「非モテ」の精神性に、迎合することです。前者をすべての個人に期待するのは社会学的に不適切です。そして後者の可能性は、すなわち自称「非モテ」の精神性には感染力がある可能性を示唆します。
もちろん、現状「非モテ」を自称されている方々に、それをやめていただくようお願いして回ることも、解決策としてはあまり正しくはないのでしょう。でも、啓蒙することに全く意味がないとは思わないので、おいらは敢えて、啓蒙しておくことにします。「非モテ」を自称するのは、なるべく控えましょう。
本質的な解決策
で、実際のところ、この問題の本質というのは、若年者を中心に、各自の承認欲求が満たされにくくなってきているっぽいという背景にあるのだと思います。これを社会的にどうにかしていきたいのであれば、子育てのあり方、教育のあり方、そしてそれらに関わる大人の時間的余裕、詰まるところ労働に関する問題、更には経済に関する問題にまで遡って、いろいろと設計し、検討する必要があるのだと思います。まぁ、一つ二つの政策であっさり解決するような問題じゃない罠。
こういう場合、近いところから修正を試みるのと、根本の方から修正を試みるのと、どっちの方がより有効なんでしょうね? この辺はもう、社会学とかまるで素人のおいらが不勉強なまま頭を捻っても、どーしようもなさそうですね。
さいごに
現状非モテを自称されている方々の中には、この記事を読んで非常に苦々しい、腹立たしい思いをされたかたも少なくないのではないかと思います。
でも、その苛立ちの理由について、今一度、自身を解体して、考えてみて欲しいとも思います。
「非モテ」という名の幻想に、帰属意識を抱いているのではありませんか?
コメント
トラックバック
このエントリのトラックバックURL: http://harapeko.asablo.jp/blog/2008/08/02/3669118/tb
※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。





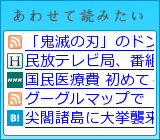





コメントをどうぞ
※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。
※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。